オフィスのキャビネットや書庫に、いつの間にか増え続ける紙の資料。いざ必要になったときに見つからなかったり、保管スペースを圧迫したりと、多くの企業で悩みの種となっています。
この問題を解決する有効な手段が「紙資料のデータ化」です。
しかし、いざデータ化を進めようと思っても、「具体的にどんな方法があるの?」「スキャナーで自分でやるべきか、それとも専門の業者に頼むべきか…」と、最初のステップで迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
実は、データ化の方法選びは、コスト、時間、品質、そしてセキュリティに大きく影響する非常に重要なポイントです。自社の状況に合わない方法を選んでしまうと、かえって非効率になったり、期待した効果が得られなかったりする可能性もあります。
この記事では、紙資料のデータ化を検討している方に向けて、「自分でやる場合」と「業者に頼む場合」の2つの方法を徹底的に比較解説します。それぞれのメリット・デメリットから具体的な手順、費用感までを網羅。この記事を読めば、あなたの会社に最適なデータ化の方法がきっと見つかります。
Contents
そもそも、なぜ今「紙資料のデータ化」が必要なのか?
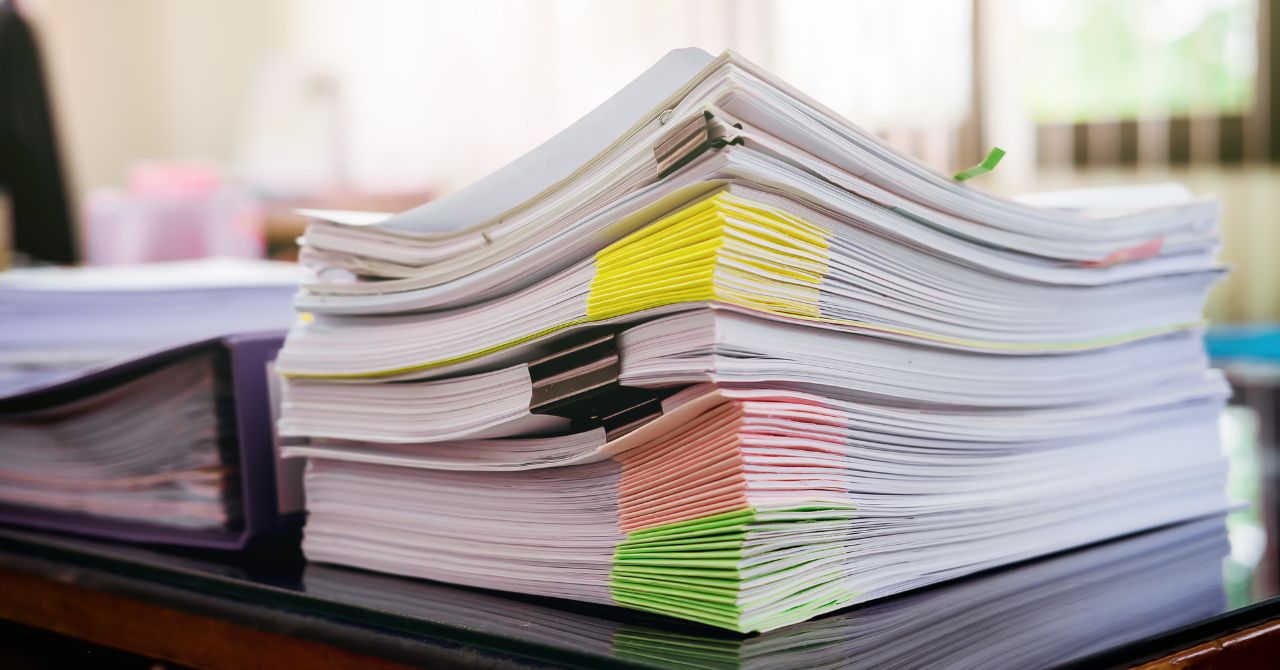
具体的な方法論に入る前に、なぜ今多くの企業が紙資料のデータ化に取り組んでいるのか、その背景とメリットを改めて確認しておきましょう。目的が明確になることで、方法選びの判断基準もよりクリアになります。
- 圧倒的な業務効率の向上: データ化された資料は、キーワード検索で一瞬で探し出せます。「あの書類どこだっけ?」と探す時間はゼロになり、社員は本来の業務に集中できます。
- コスト削減: 紙を保管するためのファイルキャビネットや外部倉庫の賃料、紙やインク代といった物理的なコストを大幅に削減できます。
- BCP(事業継続計画)対策: 地震や水害などの災害でオフィスが被害を受けても、データがクラウド上にあれば重要な経営情報を失うリスクを防げます。
- 多様な働き方への対応: 資料がデータ化されていれば、オフィス以外の場所からでもアクセス可能に。テレワークやハイブリッドワークをスムーズに導入できます。
- セキュリティ強化: 「誰が」「いつ」「どの資料に」アクセスしたかのログが残り、アクセス権限も細かく設定できるため、紙よりも格段に情報漏洩リスクを低減できます。
- 法改正への対応: 改正電子帳簿保存法により、電子取引データの電子保存が義務化されました。これを機に、紙の書類もまとめて電子化し、一元管理する流れが加速しています。
紙資料のデータ化は、もはや単なる「整理整頓」ではなく、企業の生産性や競争力、そして事業継続性を左右する重要な経営戦略なのです。
【方法1】自分で紙資料をデータ化する

まずご紹介するのは、自社のリソースを使ってスキャニングを行う方法です。比較的手軽に始められるイメージがありますが、具体的に見ていきましょう。
こんな企業におすすめ
- データ化したい紙資料の量が比較的少ない(段ボール数箱程度まで)
- とにかく初期コストを抑えたい
- 機密性が非常に高く、書類を社外に持ち出したくない
- 時間に余裕があり、自社の人員を割くことができる
自分でデータ化する具体的な手順
- 準備:スキャナーを用意します。オフィスの複合機、専用のドキュメントスキャナー、あるいはスマートフォンのスキャンアプリなどが選択肢になります。
- 仕分け・前処理:データ化する資料と不要な資料を分けます。ホチキスの針やクリップ、付箋などをすべて取り外す「前処理」は、スキャナーの故障を防ぎ、品質を保つために非常に重要です。
- スキャニング:解像度(一般的には300dpi)、カラーモード(カラー/グレースケール/白黒)、保存形式(検索可能なPDFがおすすめ)を設定し、一枚ずつスキャンしていきます。
- ファイル整理・リネーム:スキャンしたデータに分かりやすいファイル名を付けます。命名規則(例:「20240521_契約書_〇〇商事様.pdf」)を統一し、ルールに沿ってフォルダ分けすることで、後の検索性が格段に向上します。
- 保管・バックアップ:整理したデータを社内サーバーやクラウドストレージに保存します。万が一に備え、バックアップを取ることも忘れないようにしましょう。
自分でやる場合のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
| ✅ コストを抑えられる 業者への依頼費用がかからず、既存の複合機などを使えば初期投資も少なくて済みます。 |
❌ 膨大な時間と手間がかかる スキャン作業だけでなく、前処理やリネーム作業に想像以上の工数がかかります。 |
| ✅ セキュリティ面で安心 機密書類を社外に持ち出す必要がないため、物理的な輸送中の紛失や情報漏洩のリスクがありません。 |
❌ 人件費という「見えないコスト」 担当者の人件費を考えると、必ずしも安上がりとは言えません。本来の業務が圧迫される機会損失も発生します。 |
| ✅ 好きなタイミングでできる 日常的に発生する少量の書類を、その都度データ化するのに向いています。 |
❌ 品質が安定しにくい スキャン時の傾き、ゴミの写り込み、解像度のばらつきなど、品質の均一化が難しく、OCR(文字認識)の精度も低くなりがちです。 |
【方法2】専門業者に紙資料のデータ化を依頼する

次に、スキャニングを専門に行う業者にアウトソーシングする方法です。コストはかかりますが、それに見合う価値があります。
こんな企業におすすめ
- データ化したい紙資料が大量にある(段ボール10箱以上など)
- コア業務に集中するため、データ化に自社のリソースを割きたくない
- 検索精度を高めるため、OCR処理など高品質なデータを求めている
- 原本の保管や廃棄まで一括で任せたい
業者に依頼する際の一般的な流れ
- 業者選定・問い合わせ:実績やセキュリティ、料金体系を比較し、数社に見積もりを依頼します。
- 契約・書類の引き渡し:契約後、データ化したい資料を段ボールなどに詰めて業者に発送するか、業者が直接引き取りに来ます。
- スキャニング作業:業者の専門施設にて、高性能スキャナーと専門スタッフが高品質なデータ化作業を行います。OCR処理やファイル名のリネーム、インデックス作成などのオプションも依頼できます。
- データ納品・検品:DVDやハードディスク、あるいはクラウド経由でデータが納品されます。内容に問題がないか検品します。
- 原本の処理:検品後、原本を返却してもらうか、業者の機密抹消サービスで溶解処理などを依頼するかを選択します。
業者に頼む場合のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
| ✅ 時間と手間を大幅に削減 面倒な作業をすべて丸投げでき、社員はコア業務に専念できます。結果的に生産性が向上します。 |
❌ 費用がかかる スキャン枚数やオプションに応じた費用が発生します。特に少量の場合は割高になることがあります。 |
| ✅ プロ品質のデータが得られる 専用機材とノウハウにより、画像の傾き補正や白紙除去などが行われた、均一で高品質なデータが手に入ります。OCRの認識精度も高まります。 |
❌ セキュリティリスク 機密情報を外部に持ち出すため、業者選定が非常に重要です。PマークやISMS認証の有無は必ず確認しましょう。 |
| ✅ 大量の書類もスピーディーに対応 自社でやれば数ヶ月かかるような量でも、業者なら短期間で完了できます。 |
❌ 業者選定の手間がかかる 料金やサービス内容が業者によって様々なので、比較検討に時間がかかる場合があります。 |
結論:「自分でやる」vs「業者に頼む」どちらを選ぶべき?

ここまで見てきた内容を元に、あなたの会社がどちらの方法を選ぶべきか、最終的な判断基準をまとめました。
比較まとめ表
| 比較項目 | 自分でやる(DIY) | 業者に頼む |
|---|---|---|
| コスト | ◎(ただし人件費は考慮要) | △(品質・時間とのトレードオフ) |
| 時間・手間 | ❌(非常に時間がかかる) | ◎(コア業務に集中できる) |
| 品質 | △(ばらつきが出やすい) | ◎(均一で高品質) |
| セキュリティ | ◎(社外不出) | ○(信頼できる業者選定が必須) |
| おすすめのケース | ・量が少ない ・コスト最優先 ・日常的なスキャン |
・量が膨大 ・時間と品質を優先 ・過去文書の一括整理 |
【ハイブリッド案も有効!】
一つの方法に固執する必要はありません。例えば、「過去の膨大な紙資料は一度業者に頼んで一掃し、今後発生する書類は複合機で自分でデータ化する」というハイブリッドな方法も非常に賢い選択です。自社の状況に合わせて柔軟に組み合わせましょう。
重要:データ化後の「活用」を見据えた保管場所選び
紙資料のデータ化は、スキャンして終わりではありません。むしろ、データをいかに安全に保管し、効率的に活用できるかが最も重要です。せっかくデータ化しても、個人のPCや整理されていない共有フォルダに散在していては意味がありません。
データ化後の最適な保管・活用先として、今注目されているのが「クラウド文書管理システム」です。
- ファイルサーバーとの違い: サーバーは単なる「入れ物」ですが、文書管理システムは高度な検索機能、版管理、アクセス権限、承認ワークフローなど、「活用」するための機能が豊富です。
- 汎用クラウドストレージとの違い: 文書管理に特化しているため、電子帳簿保存法への対応や企業の厳格なセキュリティポリシーに準拠した設計になっています。
データ化後の活用なら「スペシウム」!電帳法にも完全対応

「データ化した資料を、どう管理・活用すればいいんだろう…」
そんなお悩みを持つ企業様に最適なのが、電帳法対応クラウド文書管理システム「スペシウム」です。
「スペシウム」は、データ化された紙資料の価値を最大限に引き出すための、強力なプラットフォームです。
<クラウド文書管理システム「スペシウム」の特長>
- ✅ 改正電子帳簿保存法に完全対応
請求書や契約書など、国税関係書類を法の要件を満たした形で安全に保存・管理できます。これからの企業コンプライアンスに必須の機能です。 - ✅ 誰でも直感的に使える操作性
ITが苦手な方でも迷わず使えるシンプルなインターフェース。導入後の社内教育もスムーズに進み、全社的な利用が定着します。 - ✅ 万全のセキュリティ体制
国内の堅牢なデータセンターでデータを管理。通信の暗号化や細やかなアクセス権限設定で、企業の重要情報を守ります。
過去の紙資料を業者に依頼して一括でデータ化し、保管先として「スペシウム」を導入しました。今では全社でペーパーレスが当たり前になり、資料探しのストレスから解放されました。特に電帳法に対応している点が、導入の決め手でした。(東京都・商社 総務部長様の声)
紙資料のデータ化は、その後の活用戦略とセットで考えることが成功の鍵です。「スペシウム」が、貴社のペーパーレス化と業務改革を力強くサポートします。
まずは、サービスの詳細が分かる資料請求や、専門スタッフによる無料相談からお気軽にお問い合わせください。


