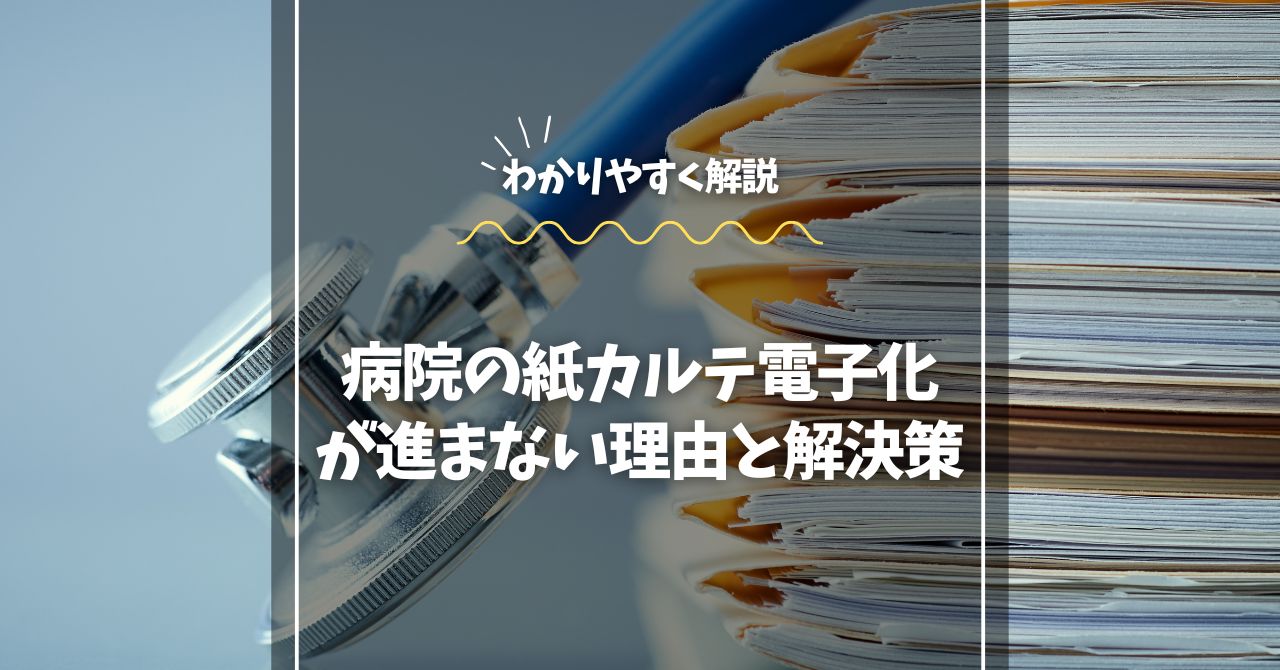医療現場のDX(デジタルトランスフォーメーション)が叫ばれる中、多くの病院で「紙カルテの電子化」が重要な課題となっています。業務効率化や医療の質の向上など、多くのメリットが期待される一方で、なかなか導入に踏み切れない病院が多いのも事実です。
「導入コストが高すぎるのでは?」「ITに詳しい職員がいない」「セキュリティは大丈夫なのか?」
このような不安から、紙媒体での運用を続けているケースは少なくありません。この記事では、なぜ病院で紙カルテや文書の電子化が進まないのか、その具体的な理由を深掘りし、それぞれの課題に対する実践的な解決策をわかりやすく解説します。記事の最後には、病院全体の文書管理を効率化するおすすめのシステムもご紹介します。
Contents
病院で紙の電子化が求められる背景

そもそも、なぜ今これほどまでに病院での紙媒体の電子化が重要視されているのでしょうか。その背景には、医療業界全体が直面しているいくつかの大きな課題があります。
- 医療従事者の負担増大:長時間労働や複雑な業務により、医療スタッフの負担は限界に近づいています。紙媒体の運用は、記録、検索、共有に多くの時間を要し、本来注力すべき患者ケアの時間を圧迫しています。
- 2024年からの医師の働き方改革:医師の時間外労働の上限規制が始まり、業務効率化は待ったなしの状況です。紙業務の電子化は、この改革に対応するための鍵となります。
- 医療情報の活用ニーズの高まり:質の高い医療を提供するためには、過去の診療記録や検査結果などのデータを迅速かつ正確に活用することが不可欠です。紙カルテでは、必要な情報を探し出すのに時間がかかり、データの横断的な分析も困難です。
- 頻発する自然災害への備え(BCP対策):地震や水害などで紙カルテが失われれば、病院機能は停止してしまいます。データを安全な場所に保管する電子化は、事業継続計画(BCP)の観点からも極めて重要です。
これらの背景から、病院における紙文書の電子化は、単なる「業務改善」ではなく、未来の医療を支えるための「必須の経営戦略」と言えるのです。
病院の紙カルテ電子化が進まない5つの理由
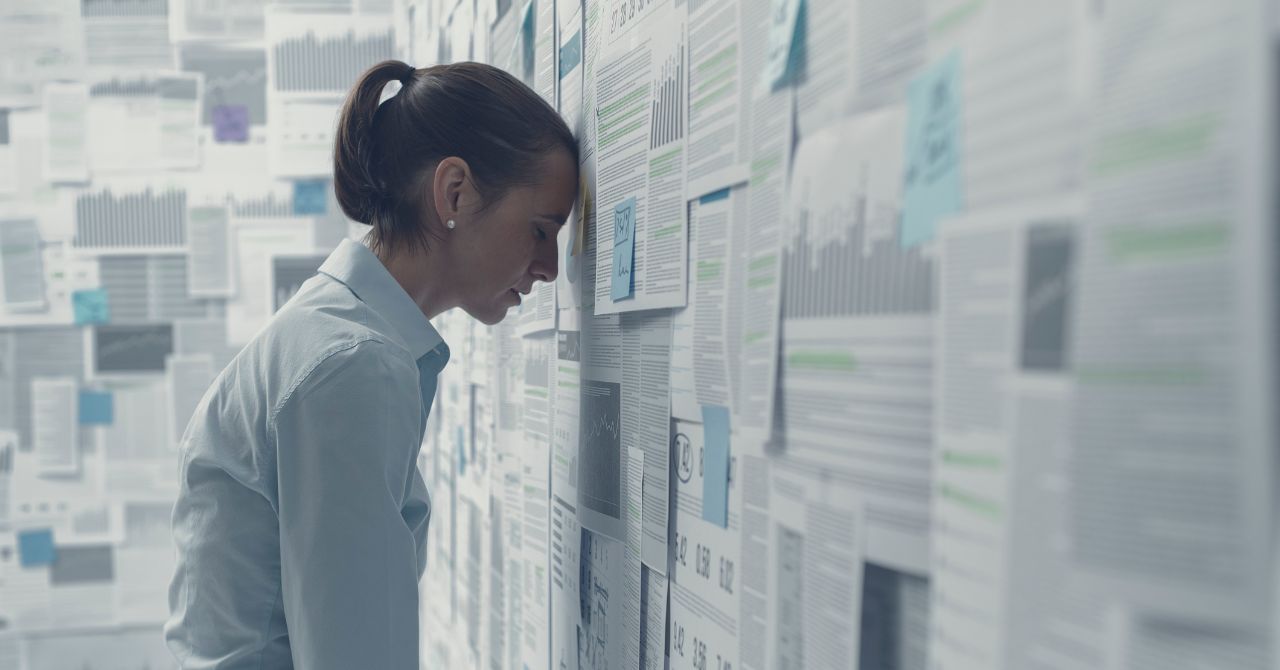
多くのメリットがあるにもかかわらず、なぜ病院の電子化は遅々として進まないのでしょうか。現場が抱えるリアルな課題は、主に以下の5つに集約されます。
1. 高額な導入・運用コストへの懸念
電子カルテシステムの導入には、サーバーや院内ネットワークの構築、ソフトウェアの購入など、数百万から数千万円規模の初期費用(イニシャルコスト)がかかる場合があります。特に中小規模の病院やクリニックにとって、この費用は大きな障壁となります。
また、導入後もシステムの保守費用やライセンス更新料といったランニングコストが発生します。費用対効果が見えにくい中で、多額の投資に踏み切るのは容易ではありません。
2. IT人材の不足と職員のITリテラシー
多くの病院では、情報システムを専門に管理する部署や人材が不足しています。システムの導入から運用、トラブル対応までを担えるIT人材がいないため、電子化プロジェクト自体を推進できないケースが少なくありません。
さらに、長年紙媒体での業務に慣れてきた医師や看護師、事務スタッフにとって、新しいシステムの操作を覚えるのは大きな負担です。「パソコン操作が苦手」「新しいことを覚える時間がない」といった声が上がり、現場スタッフからの反発を招くことも、電子化を妨げる一因となっています。
3. 情報漏洩やシステム障害へのセキュリティ不安
病院が扱うカルテ情報は、患者の命に関わる極めて機密性の高い個人情報です。そのため、電子化に伴うセキュリティリスクへの懸念は非常に大きくなります。
「サイバー攻撃を受けて情報が漏洩したらどうするのか?」
「システムがダウンして診療がストップするのではないか?」
「災害時にデータが消失する恐れはないのか?」
このような不安から、物理的に保管できる紙媒体の方が安全だと感じてしまい、電子化への移行をためらう経営者も少なくありません。
4. 既存の業務フロー変更への抵抗感
紙カルテの運用は、長年の経験の中で最適化された独自の業務フローに基づいています。電子化するということは、この慣れ親しんだ業務フローを根本から見直すことを意味します。
受付から診察、会計、検査、薬剤処方まで、院内の全部門が関わる大きな変更となるため、各部署からの調整が難航したり、「今のやり方で問題ない」という現状維持を望む声(現状維持バイアス)が強くなったりすることが、電子化の足かせとなります。
5. どのシステムを選べば良いかわからない
電子カルテシステムや文書管理システムは、国内外の多くのベンダーから提供されており、機能や価格も様々です。選択肢が多すぎるあまり、
- 自院の規模や診療科に合ったシステムはどれか
- 本当に必要な機能は何か
- 将来的な拡張性は十分か
といった点を比較検討するのが難しく、「システム選定」の段階でプロジェクトが停滞してしまうケースも多く見られます。
【理由別】病院の紙電子化を進めるための具体的な解決策

前述した「進まない理由」は、決して乗り越えられない壁ではありません。一つひとつの課題に対して、適切な対策を講じることで、スムーズな電子化を実現できます。ここでは、理由別の具体的な解決策をご紹介します。
解決策1:【コスト対策】補助金・助成金の活用とクラウド型システムの検討
高額なコストに対しては、国や自治体が提供する補助金・助成金を活用するのが有効です。代表的なものに、厚生労働省の「医療情報化支援基金」などがあります。これらの制度を積極的に活用することで、初期投資を大幅に抑えることが可能です。
また、自前でサーバーを持たずに利用できるクラウド型のシステムを選ぶのも賢い選択です。クラウド型は、
- サーバー構築が不要で、初期費用を抑えられる
- 月額利用料モデルが多く、コスト管理がしやすい
- システムの保守やアップデートはベンダー側が行うため、運用の手間が少ない
といったメリットがあり、特に中小規模の病院に適しています。
解決策2:【人材・運用対策】導入支援が手厚いベンダーを選び、段階的に導入する
IT人材が不足している場合は、導入から運用まで手厚くサポートしてくれるベンダーを選ぶことが成功の鍵です。システムの操作研修はもちろん、院内への説明会の開催や、導入後のヘルプデスクが充実しているかなどを事前に確認しましょう。
また、院内全体の業務フローを一度に変えるのではなく、「まずは一部の部署から」「まずはカルテ以外の文書から」といった形で段階的に電子化を進める(スモールスタート)のも有効です。小さな成功体験を積み重ねることで、職員の抵抗感を和らげ、徐々に院内全体へ展開していくことができます。
解決策3:【セキュリティ対策】ガイドラインへの準拠と信頼性の高いシステム選定
セキュリティ不安を解消するためには、まず国が定めるガイドラインを理解することが重要です。
| ガイドライン名 | 概要 |
|---|---|
| 3省2ガイドライン | 厚生労働省、経済産業省、総務省が策定した、医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン。システム選定時の必須要件となります。 |
| e-文書法 / 電子帳簿保存法 | カルテや会計帳簿などの国税関係書類を電子データで保存するための法律。法的要件を満たすシステムを選ぶ必要があります。 |
システム選定時には、これらのガイドラインに準拠していることはもちろん、ISO27001(ISMS)などの第三者認証を取得しているか、データの暗号化やアクセス制限機能が充実しているかなどを確認しましょう。信頼できるクラウドサービスを利用すれば、自院でサーバーを管理するよりも高いセキュリティレベルを確保できる場合も多くあります。
解決策4:【業務フロー対策】導入目的の共有と現場を巻き込んだ体制構築
業務フローの変更に対する抵抗感をなくすには、「なぜ電子化が必要なのか」という目的を経営層から現場スタッフまで全員で共有することが不可欠です。「残業を減らし、患者さんともっと向き合う時間を作るため」といった具体的なビジョンを示すことで、職員の協力を得やすくなります。
また、各部署から代表者を選出し、プロジェクトチームを組成することも重要です。システム選定や新しい業務フローの構築に現場の意見を反映させることで、「自分たちで決めたルール」という当事者意識が芽生え、スムーズな導入につながります。
解決策5:【システム選定対策】無料トライアルや導入事例を活用する
最適なシステムを選ぶためには、まず自院の課題を明確にすることが第一歩です。「待ち時間を短縮したい」「情報共有をスムーズにしたい」など、解決したい課題をリストアップしましょう。
その上で、複数のシステムを比較検討します。多くのベンダーが無料トライアル(試用期間)を提供しているので、実際に操作感を試してみるのがおすすめです。また、自院と似た規模や診療科の病院への導入事例を確認し、どのような効果があったか、どんな課題があったかなどを参考にすると、選定の失敗を防げます。
まずはカルテ以外の文書を!「スペシウム」で始める病院のペーパーレス化

ここまで病院の紙カルテ電子化について解説してきましたが、「いきなり電子カルテを導入するのはハードルが高い」と感じる方も多いかもしれません。
そこでおすすめしたいのが、まず契約書や請求書、各種申請書といった「カルテ以外の紙文書」から電子化を始めるというアプローチです。この方法なら、診療業務に直接的な影響を与えずにペーパーレス化のメリットを実感でき、職員も電子システムに慣れることができます。
そんな「はじめの一歩」に最適なのが、電帳法対応クラウド文書管理システム「スペシウム」です。
病院の文書管理における「スペシウム」の強み
「スペシウム」は、電子帳簿保存法に対応した高機能な文書管理システムであり、病院が抱える様々な紙の課題を解決します。
-
- 高度なセキュリティ:金融機関も採用する世界最高水準のセキュリティを誇るAWS(アマゾンウェブサービス)を基盤とし、ISO27001/ISO27017認証も取得。大切な文書データを安全に保管します。
- シンプルな操作性:ITに不慣れな方でも直感的に使えるデザインで、ドラッグ&ドロップで簡単に書類をアップロードできます。職員への教育コストを最小限に抑えられます。
– AI-OCRによる検索性の向上:紙の書類をスキャンしてアップロードするだけで、AI-OCRが自動でテキストを読み取ります。ファイル名だけでなく、文書内のキーワードで瞬時に検索できるため、書類探しの時間が劇的に短縮されます。
- コストを抑えた導入が可能:スモールスタートに適した料金プランが用意されており、まずは一部の部署から低コストで導入を開始できます。
- 多様な文書に対応:取引先との契約書や請求書、職員の勤怠管理表、院内の稟議書など、あらゆる紙文書を一元管理できます。
まずは総務部や経理部で扱う書類から「スペシウム」で電子化を進め、ペーパーレス化の成功体験を院内に広げていくことで、将来的な電子カルテ導入に向けた大きな足がかりとすることができます。
ご興味のある方は、ぜひ公式サイトで詳細をご確認ください。
まとめ

病院における紙カルテや文書の電子化は、コストやセキュリティ、運用面での課題から、なかなか進まないのが現状です。しかし、これらの課題は、補助金の活用、信頼できるクラウドシステムの選定、そして現場を巻き込んだ段階的な導入によって乗り越えることができます。
電子化は、もはや避けては通れない道です。本記事でご紹介した解決策を参考に、まずはできるところからペーパーレス化への一歩を踏み出し、より質の高い医療と働きやすい環境を実現してみてはいかがでしょうか。