オフィスのデスクやキャビネットが、いつの間にか書類の山になっていませんか?「必要な書類がすぐに見つからない」「保管スペースが足りない」「情報共有に時間がかかる」…こうした悩みは、多くの企業が抱える共通の課題です。
この膨大な紙媒体の書類を電子データ化する「スキャニングサービス」が、今注目を集めています。しかし、いざ利用しようと思っても、「どの業者に頼めばいいのか分からない」「料金や品質に違いはあるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
この記事では、そんなお悩みを解決するために、失敗しない紙媒体スキャニングサービスの選び方を5つの比較ポイントに絞って徹底解説します。自社に最適なサービスを見つけ、ペーパーレス化による業務効率化の第一歩を踏み出しましょう。
Contents
そもそも紙媒体スキャニングサービスとは?

紙媒体スキャニングサービスとは、企業や個人が保有する契約書、図面、領収書、会議資料といったあらゆる紙の書類を、専門の業者が預かり、高性能なスキャナーで電子データ(PDFなど)に変換してくれるサービスのことです。
単にスキャンするだけでなく、多くのサービスでは以下のような作業も含まれます。
- ホチキスやクリップの取り外し
- 書類の向きや傾きの補正
- カラー/モノクロの自動判別
- 白紙ページの削除
- OCR(光学的文字認識)処理によるテキストデータ化
- 指定されたルールに基づくファイル名の変更
- データ化した後の原本書類の保管または廃棄
自社でスキャナーを購入して作業することも可能ですが、専門のスキャニングサービスに依頼することで、圧倒的なスピードと品質、そして高いセキュリティのもとで、手間なくペーパーレス化を実現できるのが大きな魅力です。
なぜ今、紙媒体のスキャニングが必要なのか?5つのメリットを解説
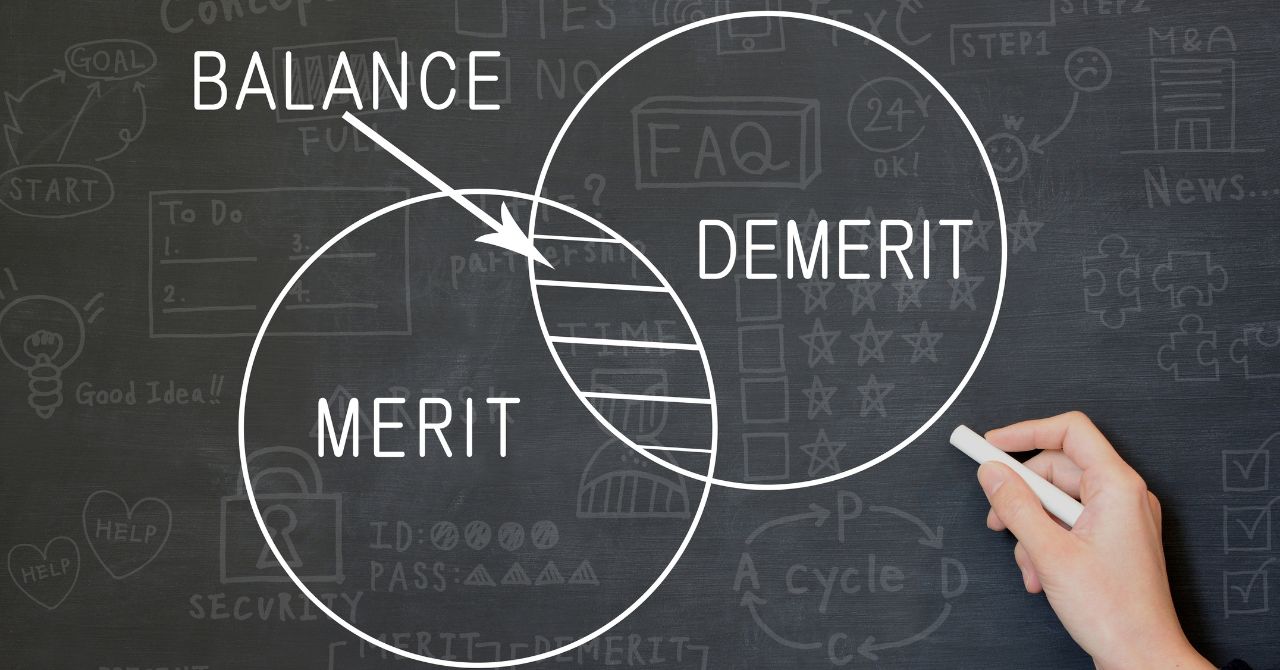
なぜ多くの企業が、コストをかけてまで紙媒体の書類をスキャニングしているのでしょうか。そこには、単に「書類が片付く」以上の、企業経営に直結する大きなメリットが存在します。
メリット1:業務効率の大幅な向上
最大のメリットは、業務効率の劇的な向上です。データ化された書類は、ファイル名や文書内のキーワードで瞬時に検索できます。キャビネットを探し回る時間はなくなり、必要な情報に数秒でアクセス可能になります。
また、データはサーバーやクラウド上で一元管理できるため、部署間での情報共有もスムーズに。承認フローの迅速化や、問い合わせ対応のスピードアップにも繋がり、組織全体の生産性を高めます。
メリット2:保管コスト・スペースの削減
紙の書類は、保管するために物理的なスペースを必要とします。オフィス内にキャビネットを置けばその分ワークスペースが狭くなりますし、外部の文書保管サービスを利用すれば継続的なコストが発生します。
スキャニングによってペーパーレス化すれば、これらの保管スペースやコストは一切不要になります。空いたスペースを有効活用したり、賃料の安いオフィスへ移転したりと、経営的なメリットも生まれます。
メリット3:セキュリティ・BCP対策の強化
紙媒体の書類は、紛失、盗難、火災、水害といった物理的なリスクに常に晒されています。一度失われれば、復元はほぼ不可能です。
データ化し、バックアップを取っておくことで、災害時でも重要な情報を守ることができます。これはBCP(事業継続計画)対策として非常に重要です。さらに、データにはアクセス権限を設定できるため、「誰が」「いつ」「どの文書に」アクセスしたかのログ管理も可能になり、内部からの情報漏洩リスクを低減させることができます。
メリット4:テレワークや多様な働き方への対応
コロナ禍以降、テレワークは一般的な働き方として定着しました。しかし、「会社に行かないとあの書類が見られない」という理由で、出社を余儀なくされるケースは少なくありません。
書類をデータ化してクラウド上で管理すれば、従業員は時間や場所を選ばずに必要な情報へアクセスできます。これにより、スムーズなテレワーク環境が実現し、育児や介護と両立しながら働く従業員を支援するなど、多様な働き方に対応できる企業体質を構築できます。
メリット5:電子帳簿保存法への対応
近年、国税関係帳簿書類の電子データ保存を認める「電子帳簿保存法(電帳法)」の要件が緩和され、多くの企業でペーパーレス化が加速しています。特に、請求書や領収書といった国税関係書類をスキャンして保存する「スキャナ保存」は、経理業務の効率化に直結します。
法令に対応した形で紙媒体をスキャニングし、適切にデータ保存することは、コンプライアンス遵守の観点からも重要性が増しています。
失敗しない!紙媒体スキャニングサービスの選び方【5つの比較ポイント】

数あるスキャニングサービスの中から、自社に最適な一社を見つけるためには、どこを比較すれば良いのでしょうか。ここでは、絶対に押さえておきたい5つの比較ポイントを詳しく解説します。
ポイント1:料金体系は明確か?
最も気になるのが料金でしょう。スキャニングサービスの料金は、一見複雑に見えることがあります。後から「こんなはずでは…」とならないよう、料金体系をしっかり確認しましょう。
■基本料金
基本料金は、スキャンする書類1枚あたりの単価で設定されていることがほとんどです。「A4サイズ モノクロ 〇円」「A3サイズ カラー 〇円」のように、サイズやカラー/モノクロによって価格が変わります。
■オプション料金
注意すべきはオプション料金です。基本料金が安くても、必要な作業がすべてオプション扱いで、結果的に高額になるケースがあります。以下の項目が基本料金に含まれるのか、オプションなのかを確認しましょう。
- ホチキスやクリップの取り外し・付け直し
- ファイルやバインダーからの取り出し・戻し
- OCR処理(テキスト検索可能PDFの作成)
- ファイル名の変更(リネーム)
- スキャン後の原本廃棄
- 特急対応
【料金比較テーブルの例】
| 項目 | A社 | B社 | C社 |
|---|---|---|---|
| A4モノクロ単価 | 3.0円~ | 3.5円~ | 2.8円~ |
| OCR処理 | +1.0円/枚 | 基本料金に含む | +1.5円/枚 |
| ファイル名変更 | +10円/ファイル | +15円/ファイル | +8円/ファイル |
| ホチキス外し | 基本料金に含む | 要見積もり | 基本料金に含む |
※上記はあくまで一例です。実際の料金は各サービスにご確認ください。
必ず複数の業者から相見積もりを取り、作業内容と総額を比較検討することが重要です。
ポイント2:セキュリティ対策は万全か?
会社の機密情報や個人情報を含む書類を外部に預けるのですから、セキュリティ対策は最も重要なチェックポイントです。
【セキュリティのチェック項目】
✅ プライバシーマーク(Pマーク)やISMS(ISO27001)認証を取得しているか?
✅ 作業場所は部外者が立ち入れないよう、入退室管理が徹底されているか?
✅ 監視カメラは設置されているか?
✅ 書類の輸送方法や保管方法は安全か?
✅ 作業スタッフとの間で機密保持契約を締結しているか?
✅ データ納品後の原本や作業データの廃棄方法は適切か?(溶解処理証明書の発行など)
企業のウェブサイトでセキュリティポリシーを確認するだけでなく、問い合わせの際に具体的な対策内容を質問し、安心して任せられる業者を選びましょう。
ポイント3:スキャニングの品質は十分か?
せっかくデータ化しても、文字が潰れて読めなかったり、図面が不鮮明だったりしては意味がありません。スキャニングの品質を左右する要素を理解しておきましょう。
- 解像度(dpi):数値が高いほど高精細になります。一般的な文書なら200~300dpi、図面や写真なら400~600dpiが目安です。
- カラーモード:カラー、グレースケール、モノクロ2値から選びます。契約書の印影など、色情報が重要な場合はカラーでのスキャンが必要です。
- 画像補正:傾き補正、文字の向き補正、裏写り防止、ノイズ除去といった機能が充実しているかを確認します。
- OCR精度:テキスト検索の精度に直結します。特に手書き文字や古い印刷物が多い場合は、OCRの精度が高い業者を選ぶことが重要です。
多くの業者では、無料のお試しスキャンを提供しています。契約前に自社の書類を数枚スキャンしてもらい、品質に納得できるか自分の目で確かめることを強くおすすめします。
ポイント4:対応できる書類の種類とサイズは?
「依頼しようとしたら、この書類は対応できないと断られた」という事態を避けるため、自社がスキャンしたい書類の種類とサイズに対応しているか事前に確認しましょう。
一般的なA4・A3サイズの書類だけでなく、以下のような特殊な原稿への対応可否もポイントです。
-
- 大判図面(A2~A0):建設業や製造業では必須です。
- 契約書などの製本された書類:裁断せずにスキャンできるか(非破壊スキャン)。
– 領収書や名刺などの小サイズ・不定形な書類
- 劣化の激しい古い書類や和紙
- ホチキスや付箋がついたままの書類
自社の書類の特性を把握し、柔軟に対応してくれるスキャニングサービスを選びましょう。
ポイント5:納品形式と納期は希望通りか?
最後に、納品に関する希望を叶えてくれるかも重要です。
■納品形式
一般的な納品形式はPDFですが、他にもJPEG、TIFFなど様々な形式があります。用途に合わせて指定できるか確認しましょう。また、PDFにも種類があります。
- 検索可能PDF(サーチャブルPDF):OCR処理により、見た目は画像ですがテキスト情報が埋め込まれており、キーワード検索が可能な形式。最もおすすめの形式です。
- 通常のPDF:単なる画像データとしてのPDF。検索はできません。
■ファイル名の命名規則(リネーム)
データ化した後の管理を容易にするため、ファイル名の付け方は非常に重要です。「契約書_取引先名_日付.pdf」のように、自社のルールに沿って柔軟にリネームしてくれるかを確認しましょう。
■納期
「いつまでにデータが必要か」というスケジュールも大切です。書類の量や作業内容によって納期は変動しますが、標準的な納期はどれくらいか、急いでいる場合の特急対応は可能か、といった点も確認しておくと安心です。
スキャン後のデータ活用を最大化するならクラウド文書管理システムがおすすめ
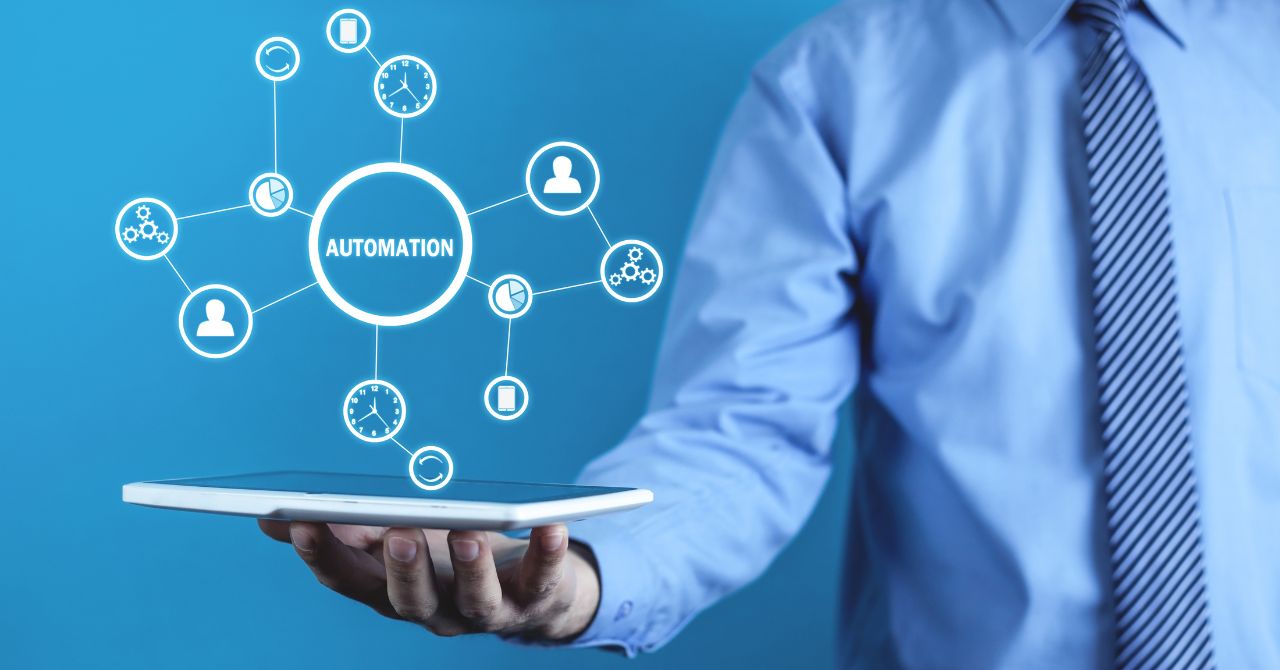
紙媒体のスキャニングサービスを利用して書類をデータ化することは、ペーパーレス化の重要な第一歩です。しかし、ただデータ化しただけでは、その効果を半分しか得られていません。
データ化された大量のファイルを、個人のPCや共有フォルダでバラバラに管理していては、結局「あのファイルはどこだっけ?」という問題が再発してしまいます。また、セキュリティ面でも不安が残ります。
そこで重要になるのが、スキャンした後の「データの受け皿」です。その最適なソリューションが、クラウド文書管理システムです。
クラウド文書管理システムを導入すれば、スキャンしたデータを一元的に保管し、高度な検索機能、厳格なアクセス権限管理、版管理(バージョン管理)、承認ワークフローといった機能を使って、データを安全かつ効率的に「活用」する体制を構築できます。
【PR】電帳法にも対応!クラウド文書管理システムなら「スペシウム」

スキャニング後の文書管理でお悩みなら、電帳法対応クラウド文書管理システム「スペシウム」がおすすめです。
「スペシウム」は、紙媒体のスキャニングでデータ化した書類の価値を最大限に引き出すための機能を多数搭載しています。
<スペシウムの主な特徴>
- AI-OCRによる高精度なデータ化
請求書や領収書などをアップロードするだけで、AI-OCRが自動で読み取り、インデックス情報を自動入力。手入力の手間を大幅に削減します。 - 安心の電子帳簿保存法対応
JIIMA(日本文書情報マネジメント協会)の「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」「電子取引ソフト法的要件認証」を取得。法令に準拠した形で、安心して国税関係書類を電子保存できます。 - 誰でも使えるシンプルな操作性
直感的で分かりやすいインターフェースで、ITツールが苦手な方でも簡単に操作できます。導入後の社内教育コストも抑えられます。 - 柔軟な権限設定と高度なセキュリティ
部署や役職ごとに細かくアクセス権限を設定可能。閲覧、編集、削除などの操作を制限し、不正なアクセスや情報漏洩を防ぎます。 - 各種システムとのAPI連携
既にお使いの会計システムや販売管理システムと連携させることで、さらなる業務効率化を実現できます。
紙媒体のスキャニングサービスで書類の電子化を進め、その受け皿として「スペシウム」を活用することで、検索性の向上、コスト削減、セキュリティ強化といったメリットを最大化し、真のペーパーレス化とDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進できます。
まとめ
今回は、オフィスの書類の山を解決する紙媒体スキャニングサービスの選び方について、5つの比較ポイントを中心に解説しました。
- 料金体系は明確か?(総額で比較する)
- セキュリティ対策は万全か?(認証取得や施設を確認)
- スキャニングの品質は十分か?(無料お試しを活用)
- 対応できる書類の種類とサイズは?(特殊な原稿も確認)
- 納品形式と納期は希望通りか?(活用を見据える)
これらのポイントを押さえ、複数の業者を比較検討することで、自社のニーズに合った最適なパートナーを見つけることができるはずです。そして、スキャンして終わりではなく、「スペシウム」のようなクラウド文書管理システムを活用して、データを資産として経営に活かしていくことが、これからの企業に求められます。
まずは気になるスキャニングサービスに問い合わせ、見積もりや無料お試しから始めてみてはいかがでしょうか。その一歩が、あなたの会社の未来を大きく変えるかもしれません。


