現代ビジネスにおいて、紙媒体の文書は依然として多くの企業で利用されています。しかし、その管理や検索、保管には多くの時間とコストがかかります。そこで注目されているのが、「文書データ化サービス」です。
紙の文書をデジタルデータに変換することで、業務効率化やコスト削減、セキュリティ強化など、多くのメリットが期待できます。しかし、いざサービスを検討しようとすると、「料金はどのくらい?」「どんなサービスがあるの?」「自社に合ったサービスはどう選べばいいの?」といった疑問に直面するのではないでしょうか。
本記事では、そんな疑問を解消するため、文書データ化サービスの料金相場を徹底解説し、貴社に最適なサービスを見つけるための重要な選定ポイントを詳しくご紹介します。文書データ化サービスの導入を検討されている方は、ぜひ最後までお読みください。
Contents
文書データ化サービスとは?その必要性

文書データ化サービスとは、企業が保有する紙媒体の文書(契約書、請求書、帳票、図面、カルテなど)を専門業者がデジタルデータ(PDF、TIFF、JPEGなど)に変換するサービス全般を指します。
単にスキャンするだけでなく、文字認識(OCR処理)によるテキストデータ化、ファイル名の自動付与、検索用インデックス情報の付与、既存システムへの連携サポートなど、多岐にわたるサービスを提供しています。
なぜ今、文書データ化サービスが必要とされているのか?
紙媒体の文書は、保管スペースの確保、必要な情報へのアクセス時間、災害時のリスク、情報漏洩のリスクなど、様々な課題を抱えています。特に、近年では「電子帳簿保存法」の改正により、多くの企業で文書の電子化が喫緊の課題となっています。
文書データ化サービスを利用することで、これらの課題を解決し、以下のような具体的なメリットを享受できます。
文書データ化サービスの主なメリット
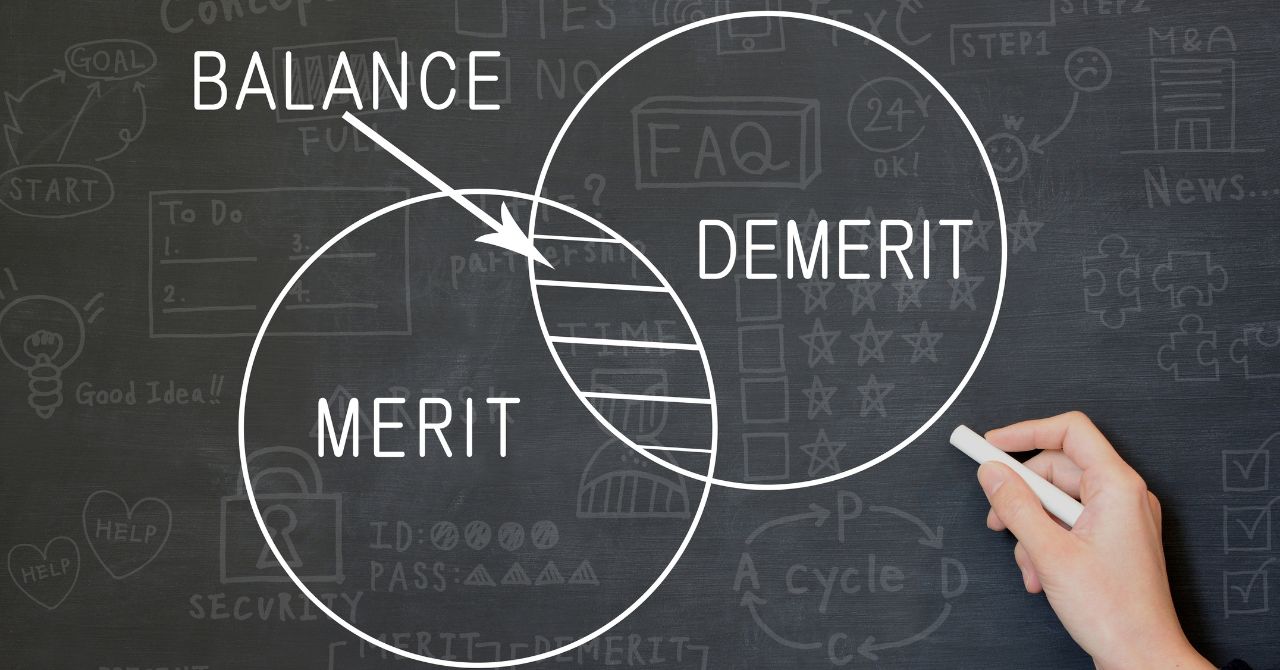
文書データ化サービスを導入することで得られる具体的なメリットは多岐にわたります。ここでは、主要なメリットを詳しく見ていきましょう。
1. 業務効率の大幅な向上
- 検索性の向上: 紙の文書を探す手間がなくなり、PCやタブレットからキーワードで瞬時に必要な文書を見つけられます。これにより、業務のスピードアップと従業員のストレス軽減に繋がります。
- 情報共有の迅速化: データ化された文書はネットワークを通じて簡単に共有できます。複数拠点での同時閲覧や、リモートワーク環境下での情報共有もスムーズになり、コラボレーションが促進されます。
- 事務作業の削減: 閲覧、コピー、ファイリングといった紙文書特有の作業が不要になり、従業員がより生産的な業務に集中できる時間を生み出します。
2. コストの削減
- 保管コストの削減: 大量の紙文書を保管するためのオフィススペースやキャビネットが不要になり、賃料や設備費を削減できます。
- 印刷・消耗品費の削減: 文書の共有や閲覧がデジタル化されることで、印刷用紙やトナーなどの消耗品費、さらには印刷機器の維持管理費も削減できます。
- 人件費の削減: 文書管理にかかる労力や時間が減ることで、その分の人件費を削減したり、他の業務に再配置したりすることが可能です。
3. セキュリティの強化とコンプライアンス対応
- 情報漏洩リスクの低減: 紙文書は紛失や盗難、誤廃棄による情報漏洩のリスクがつきまといます。データ化された文書は、アクセス制限、ログ管理、暗号化などのセキュリティ対策を講じることで、物理的なリスクを大幅に低減できます。
- 災害リスクの分散: 火災や水害などの災害で物理的な文書が失われるリスクを回避できます。クラウド上にデータを保管することで、BCP(事業継続計画)対策としても有効です。
- 電子帳簿保存法への対応: 多くの企業が直面している電子帳簿保存法の要件を満たす上で、文書データ化は不可欠な第一歩となります。サービスによっては、電帳法対応のためのスキャン要件やタイムスタンプ付与などもサポートしてくれます。
4. 環境への配慮
- ペーパーレス化は、紙の使用量を減らすことで森林保護に貢献し、環境負荷の低減にも繋がります。企業のCSR(企業の社会的責任)活動の一環としてもアピールできます。
これらのメリットを総合的に考慮すると、文書データ化サービスの導入は、企業の競争力強化と持続可能な経営に貢献すると言えるでしょう。
文書データ化サービスの料金体系と相場
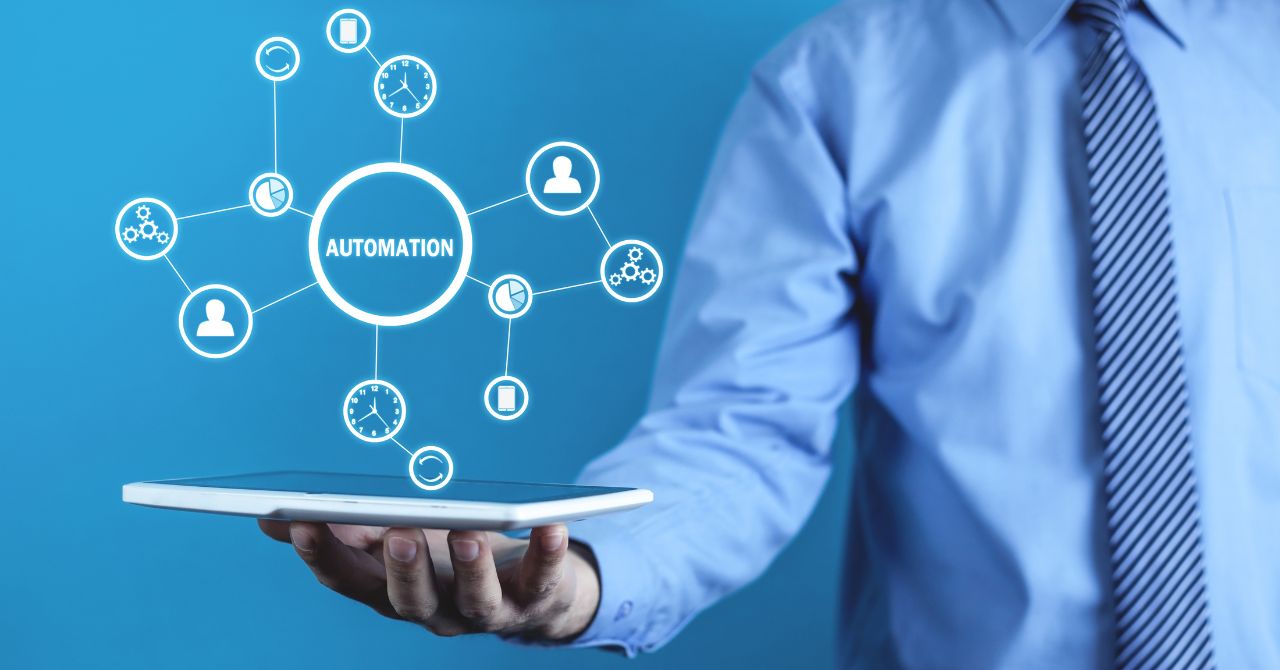
文書データ化サービスの料金は、提供会社や依頼内容によって大きく変動します。ここでは、一般的な料金体系と、料金に影響を与える主要な要素、そして料金相場について詳しく解説します。
料金体系の種類
主に以下の3つの料金体系があります。
- 単価制(従量課金制): スキャンする文書1枚あたり、または1ファイルあたりの単価が設定される最も一般的な形式です。文書の量に応じて料金が決まるため、小ロットから大量の文書まで幅広く対応できます。
- 月額制(定額制): 一定期間内にスキャンできる枚数や、クラウドストレージの容量に応じた月額料金が設定されます。定期的に大量の文書が発生する場合や、データ管理システムも併せて利用する場合に採用されることがあります。
- プロジェクト制: 大規模な初期データ化プロジェクトや、特殊な文書(古文書、大型図面など)のデータ化、コンサルティングを含む場合に採用されます。見積もりベースで、トータル費用が提示されます。
料金に影響を与える主な要素
文書データ化サービスの料金は、以下の要素によって大きく変動します。
- 文書の種類とサイズ: A4、A3などの定型サイズか、不定形なものか。契約書、請求書、図面、書籍など、文書の種類によって手間が変わります。
- 文書の状態: ホッチキス止め、クリップ止め、付箋の有無、ページの破損、糊付けなど、事前処理の手間がかかるほど料金は高くなります。
- データ化する枚数(量): 枚数が多ければ多いほど、一枚あたりの単価は安くなる傾向があります(ボリュームディスカウント)。
- カラー/モノクロ: カラー文書のスキャンは、モノクロに比べて単価が高くなります。
- OCR処理の有無と精度: 画像データだけでなく、テキスト検索を可能にするためのOCR(光学文字認識)処理を行うかどうか。OCR処理の精度や対応言語によって料金が変わります。
- 納品形式: PDF、TIFF、JPEGなど、特定のファイル形式への変換。検索可能なPDF(サーチャブルPDF)は単価が高くなります。
- 付帯サービス:
- データ入力・インデックス付与: ファイル名ルールに沿った命名、検索用キーワードやメタデータの手動入力など、手間のかかる作業は追加料金が発生します。
- ファイリング・分類: データ化後の文書の物理的な整理や、指定されたフォルダー構造への格納。
- 出張スキャン: 文書の持ち出しが困難な場合に、現地でスキャンを行うサービス。
- 書類廃棄: データ化後の文書の溶解処理や機密抹消処理。
- 文書管理システム連携: 既存の文書管理システムやクラウドサービスへのアップロード代行、API連携サポートなど。
- 納期: 特急対応など、短納期を希望する場合は追加料金が発生することがあります。
文書データ化サービスの料金相場(目安)
あくまで目安ですが、一般的な文書データ化サービスの料金相場は以下の通りです。実際の料金は、複数の業者から見積もりを取得して比較検討することが重要です。
| サービス内容 | 料金相場(1枚あたり) | 備考 |
|---|---|---|
| A4モノクロスキャン(OCRなし) | 10円~30円 | 基本スキャンのみ、枚数が多いほど単価は安くなります。 |
| A4モノクロスキャン(OCRあり) | 20円~50円 | 検索可能なPDF作成など。 |
| A4カラースキャン(OCRなし) | 30円~70円 | 図面や写真が含まれる文書など。 |
| A4カラースキャン(OCRあり) | 40円~100円 | カラー文書の検索性向上。 |
| データ入力・インデックス付与 | 10円~50円(項目数による) | 手作業による付与の場合。 |
| 事前処理(ホッチキス外しなど) | 5円~20円(手間による) | 文書の状態によって変動。 |
| 大型図面スキャン(A0など) | 数百円~数千円 | 特殊なスキャナーが必要。 |
※上記はあくまで目安であり、最低ロット数や契約内容によって実際の価格は異なります。
【重要】料金比較の際は、必ず「トータルコスト」で比較検討しましょう。
単価が安くても、オプション費用や付帯サービスが別途高額になるケースもあります。また、サービス品質が低いと、後で修正や再作業が発生し、かえってコストがかさむこともあります。必ず複数社から詳細な見積もりを取り、サービス内容と料金のバランスを見極めることが重要です。
文書データ化サービス選定の重要ポイント

文書データ化サービスの導入を成功させるためには、料金だけでなく、様々な側面からサービスを比較検討する必要があります。ここでは、サービス選定において特に重要なポイントを詳しく解説します。
1. 目的と要件の明確化
文書データ化の目的を明確にすることが、最適なサービス選定の第一歩です。「なぜ文書をデータ化するのか?」「何を解決したいのか?」を具体的にしましょう。
- データ化する文書の種類と量: 契約書、請求書、図面、カルテなど、文書の種類や量(枚数、ファイル数)を把握します。
- データ化の目的: 業務効率化、コスト削減、セキュリティ強化、電帳法対応、BCP対策など。
- 必要なデータ形式と検索性: 閲覧ができれば良いのか、キーワード検索が必要なのか、既存システムへの連携が必要かなど。
- セキュリティレベル: 機密性の高い文書が含まれるか、ISMS(ISO27001)などの認証が必要か。
2. 提供サービス内容と専門性
データ化の質や効率は、提供されるサービス内容と業者の専門性に大きく左右されます。
- スキャン品質と技術力: 高解像度スキャン、OCR技術の精度、特殊文書(綴じ込み、破損、大型など)への対応力。
- 対応できる文書の種類: 一般文書だけでなく、マイクロフィルム、大判図面、古文書など、特殊な文書に対応可能か。
- OCR処理の対応範囲: 日本語だけでなく、多言語対応の有無。手書き文字認識の精度。
- データ入力・インデックス付与の柔軟性: 貴社のファイル名ルールや、検索に必要なメタデータ(日付、顧客名、種類など)を正確に付与できるか。
- コンサルティング能力: データ化後の運用も含めて、最適な提案をしてくれるか。
- 実績と事例: 自社と同業種や同規模の企業での導入実績があるか。具体的な成功事例を確認しましょう。
3. 料金体系と見積もりの透明性
前述の通り、文書データ化サービスの料金は複雑です。料金体系の透明性と見積もりの詳細をしっかり確認しましょう。
- 見積もりの明確さ: 費用項目が明確か、追加料金が発生する可能性について説明があるか。
- 初期費用と月額費用: 一度限りの費用なのか、継続的な費用が発生するのか。
- ボリュームディスカウントの有無: 大量発注時の割引制度があるか。
- コストパフォーマンス: 単に安いだけでなく、提供されるサービスの品質や付帯サービスを含めて、総合的なコストパフォーマンスを評価しましょう。
4. セキュリティ対策とプライバシー保護
文書には機密情報が含まれることが多いため、セキュリティ対策は最も重要な選定ポイントの一つです。
- 情報管理体制: 文書の受け渡しからデータ化、納品、廃棄までの各工程で、どのようなセキュリティ対策が取られているか。
- 認証取得状況: ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)やプライバシーマークなどの第三者認証を取得しているか。
- 従業員の教育: 文書を扱う従業員に対するセキュリティ教育が徹底されているか。
- データ保管場所と期間: データ化後のデータ保管方法(クラウド、オンプレミス)、保管場所、保管期間、そして廃棄時の方法。
- 物理的セキュリティ: 文書保管場所の入退室管理、監視体制など。
5. サポート体制と導入後のフォロー
導入後のスムーズな運用のためには、充実したサポート体制が不可欠です。
- 導入支援: データ化プロジェクトの計画立案から実行までの支援があるか。
- トラブル時の対応: 問題が発生した際の対応スピードや、連絡体制。
- 質問への対応: 疑問点や不明点に対する問い合わせ窓口の有無と対応の質。
- アフターサービス: データ化後の文書管理システムへの連携支援や、運用に関するコンサルティングなど。
6. 納品形式と既存システムとの連携
データ化された文書の活用方法を考慮し、納品形式と既存システムとの連携がスムーズに行えるかを確認しましょう。
- 多様な納品形式: PDF(検索可能PDF)、TIFF、JPEG、CSVなど、貴社が必要とする形式に対応しているか。
- ファイル名ルールの適用: 貴社の指定するファイル名ルール(日付+文書名+顧客名など)に沿って命名してくれるか。
- 既存システムとの連携: 既に利用している文書管理システム、ERP、CRMなどとのデータ連携が可能か、API提供の有無など。
7. 納期と対応スピード
大量の文書をデータ化する場合や、緊急でデータ化が必要な場合は、納期と対応スピードも重要な要素です。
- 処理能力: 大量の文書を短期間で処理できる体制があるか。
- 柔軟な対応: 急な増量や内容変更など、柔軟に対応してくれるか。
- スケジュール管理: データ化プロジェクトの進行状況を定期的に報告してくれるか。
これらのポイントを総合的に評価し、複数の業者から詳細な情報と見積もりを取得することで、貴社に最適な文書データ化サービスを見つけることができるでしょう。
料金を抑えるヒント

文書データ化サービスの料金をできるだけ抑えたい場合、以下の点を考慮することでコストを削減できる可能性があります。
- データ化する文書の選別: すべての文書をデータ化する必要があるか再検討しましょう。利用頻度の低いものや、保管義務のないものは、廃棄を検討したり、優先順位を下げたりすることで、データ化する量を減らせます。
- 自社でできることと依頼する範囲の切り分け: ホッチキス外しやクリップ除去などの事前準備、あるいは簡単なファイリングなどは自社で行うことで、業者に支払う手間賃を削減できます。
- OCR処理の要不要の検討: 全ての文書にOCR処理が必要か検討しましょう。閲覧のみで十分な文書であれば、OCR処理を省略することでコストを抑えられます。
- 納品形式の選択: 検索可能なPDFなど高機能な形式はコストが高くなる傾向があります。単なる画像データで十分な場合は、シンプルな形式を選択しましょう。
- 複数社からの見積もり取得と交渉: 複数の業者から見積もりを取り、比較検討することで、最も費用対効果の高いサービスを見つけやすくなります。また、相見積もりを提示して交渉することで、料金が下がる可能性もあります。
- 定期的な契約の見直し: 長期契約を検討している場合は、定期的に契約内容や料金プランを見直すことで、より効率的なプランに切り替えることができるかもしれません。
文書データ化サービス導入時の注意点
文書データ化サービスの導入を検討する際には、いくつか注意しておくべき点があります。
- 契約内容の徹底的な確認: 見積もり内容、サービス範囲、納期、責任範囲、個人情報保護に関する取り決めなど、契約書の内容を隅々まで確認し、不明点は必ず事前に解消しておきましょう。
- サンプルスキャンでの品質確認: 大量の文書を依頼する前に、一部の文書でサンプルスキャンを依頼し、スキャン品質、OCR精度、ファイル名付与の正確性などを確認することをおすすめします。
- 電子帳簿保存法への対応要件: 特に、電子帳簿保存法(電帳法)の要件を満たすためにデータ化を行う場合は、解像度、階調、タイムスタンプ、検索機能などの要件をサービスプロバイダーが満たしているか、具体的な方法を確認しておく必要があります。
- データ化後の運用体制: データ化が完了した後、そのデータをどのように管理し、活用していくかという運用体制を事前に構築しておくことが重要です。適切な文書管理システムがないと、せっかくデータ化しても十分に活用できない可能性があります。
- 原本の取り扱い: データ化された後の紙の原本をどうするか(返却、廃棄、一定期間保管など)を事前に決めておきましょう。機密文書の廃棄には専門業者による溶解処理などを検討することも重要です。
【特別紹介】電帳法対応クラウド文書管理システム「スペシウム」

文書データ化サービスによって、貴社の紙文書はデジタル化され、その利便性は飛躍的に向上します。しかし、データ化された文書を「いかに効率的に管理し、安全に活用するか」もまた、非常に重要な課題です。
そこでご紹介したいのが、電帳法対応クラウド文書管理システム「スペシウム」です。
スペシウムは、電子帳簿保存法に対応したクラウド型文書管理システムです。インボイス制度や電子帳簿保存法への対応はもちろん、文書の検索性向上、厳格なアクセス制限、証跡管理など、企業のデジタル化を強力に推進します。
経理処理の効率化だけでなく、契約書や稟議書などあらゆる文書の一元管理を可能にし、情報共有の促進、内部統制の強化を実現します。
「スペシウム」は、データ化された文書を安全かつ効率的に管理するために設計されており、特に以下のようなメリットを提供します。
- 電子帳簿保存法に完全対応: スキャナ保存や電子取引データの保存要件を満たし、タイムスタンプ付与機能や検索機能など、電帳法対応に必要な機能を網羅しています。
- 優れた検索性: 文書データ化サービスで付与された情報や、OCR処理でテキスト化された内容から、必要な文書を素早く検索・特定できます。
- 堅牢なセキュリティ: クラウド環境で強固なセキュリティ対策を施しており、不正アクセスや情報漏洩のリスクを最小限に抑えます。アクセス権限設定や操作ログの記録も可能です。
- 一元管理と情報共有: 経理書類だけでなく、契約書、稟議書、顧客情報など、社内のあらゆる文書をクラウド上で一元管理。必要な情報にいつでもどこからでもアクセスでき、情報共有をスムーズにします。
- ワークフロー連携: 承認フローなど、既存の業務フローと連携することで、業務効率をさらに向上させることが可能です。
文書データ化サービスでデジタル化された文書を、「スペシウム」のようなクラウド文書管理システムで適切に運用することで、単なるペーパーレス化に留まらず、企業の生産性向上、内部統制の強化、そして新たな価値創造に繋がるでしょう。
詳細はこちらをご覧ください:
電帳法対応クラウド文書管理システム「スペシウム」
まとめ
本記事では、文書データ化サービスの料金体系と相場、そして最適なサービスを選定するための重要なポイントを詳しく解説しました。文書データ化は、業務効率化、コスト削減、セキュリティ強化、そして電子帳簿保存法への対応といった多くのメリットをもたらします。
文書データ化サービスの料金は、文書の種類や量、付帯サービスによって大きく変動するため、複数の業者から詳細な見積もりを取得し、サービス内容とコストのバランスを慎重に比較検討することが成功の鍵となります。また、セキュリティ対策や導入後のサポート体制も重要な選定基準です。
データ化された文書を最大限に活用するためには、電帳法対応クラウド文書管理システム「スペシウム」のようなツールと連携することで、より安全かつ効率的な文書管理が実現できます。
貴社のニーズに合った最適な文書データ化サービスを見つけ、デジタル変革を推進する一助となれば幸いです。


