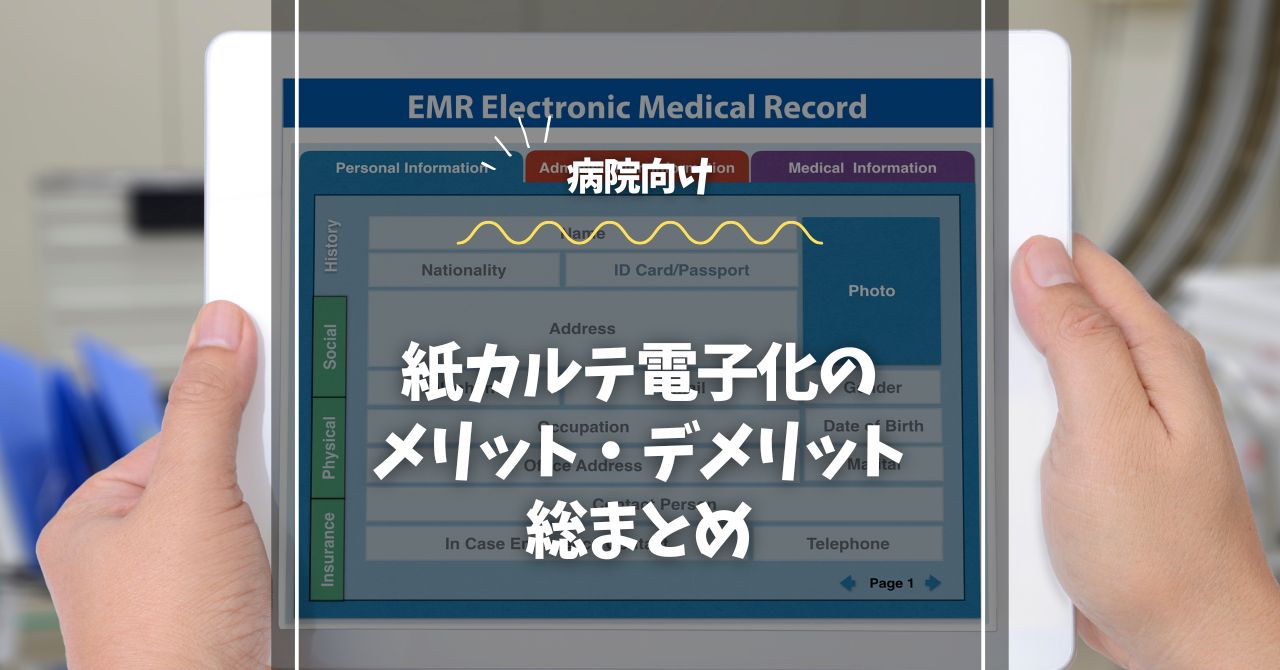病院の院長先生、事務長様、そして医療現場の皆様、このような課題に直面していませんか?
- カルテ庫が満杯で、保管スペースの確保が限界にきている…
- 必要なカルテを探し出すのに時間がかかり、患者様の待ち時間が長引いてしまう…
- 医師の字が判読しづらく、ヒヤリ・ハットの原因になったことがある…
- 多職種間での情報共有がスムーズにいかず、チーム医療の推進に壁を感じる…
これらの課題は、多くの病院が抱える共通の悩みです。そして、その根本的な解決策となるのが「紙カルテの電子化」です。
国が推進する医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の波に乗り、診療の質向上と業務効率化を両立させるために、電子カルテシステムの導入はもはや避けては通れない重要な経営判断となっています。
しかし、導入には多額のコストがかかる上、現場のオペレーションも大きく変わるため、メリットだけでなくデメリットも正確に把握した上で慎重に検討したい、とお考えのことでしょう。
この記事では、病院における紙カルテ電子化のメリット・デメリットを徹底的に比較・解説し、導入を成功に導くためのポイントを総まとめします。
Contents
そもそも「紙カルテの電子化」とは?

「紙カルテの電子化」とは、一般的に「電子カルテシステム(EMR: Electronic Medical Record)」を導入し、これまで紙で記録・保管していた診療情報を電子データとして一元管理することを指します。
単に紙カルテをスキャナーで読み取ってPDF化する「スキャニング保存」とは異なり、電子カルテシステムは診療情報の記録、参照、共有、さらにはオーダリングシステムや医事会計システムとの連携など、院内の情報フロー全体を効率化する総合的な仕組みです。
厚生労働省は「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を定めており、電子カルテの導入・運用においては、情報の真正性、見読性、保存性の3つの原則を満たすことが求められています。信頼できるベンダーのシステムを選ぶことが極めて重要です。
以下に、紙カルテと電子カルテの主な違いをまとめました。
| 項目 | 紙カルテ | 電子カルテ |
|---|---|---|
| 記録方法 | 手書き | キーボード入力(テンプレート機能あり) |
| 保管場所 | 院内のカルテ庫(物理的スペースが必要) | 院内サーバー or クラウド(物理的スペース不要) |
| 検索性 | IDや氏名で手作業検索(時間がかかる) | キーワード、日付、病名などで瞬時に検索可能 |
| 同時閲覧 | 不可能(1冊しかないため) | 可能(複数人が同時にアクセスできる) |
| 判読性 | 書き手によって差が大きい(判読困難な場合も) | 誰が読んでも同じ(活字) |
| データ連携 | 困難(手入力での転記作業が必要) | 医事会計、検査、画像システム等と容易に連携 |
| 災害時 | 紛失、焼失、水損のリスクが高い | バックアップによりデータ保全が可能 |
病院が紙カルテを電子化する7つのメリット

紙カルテの電子化は、病院経営と医療現場に多岐にわたるメリットをもたらします。ここでは代表的な7つのメリットを詳しく見ていきましょう。
メリット1:医療の質の向上と医療安全の確保
最も大きなメリットは、患者様へ提供する医療の質と安全性が向上することです。
- 判読性の向上: 手書きによる判読ミスがなくなり、薬剤の誤投与や指示の誤解といった医療過誤のリスクを大幅に低減できます。
- 情報へのアクセス性向上: 過去の診療記録、アレルギー情報、禁忌薬などを瞬時に確認できるため、より的確な診断と治療計画の立案が可能になります。
- チェック機能の活用: 医薬品の相互作用やアレルギーに関するアラート機能など、システムによるチェックが働くことで、ヒューマンエラーを防ぎます。
メリット2:業務効率の大幅な向上
医療スタッフの業務負担を軽減し、本来の専門業務に集中できる環境を整えます。
- カルテの検索・運搬時間の削減: 診察室、病棟、ナースステーションなど、必要な場所で即座にカルテを呼び出せるため、カルテを探し回る時間や部署間を運搬する手間がゼロになります。
- 入力作業の効率化: 定型文を登録できるテンプレート機能や過去の記載をコピーする機能により、カルテ入力の時間を短縮できます。
- 事務作業の自動化: 診察内容が医事会計システムに自動で連携されるため、会計待ち時間の短縮や請求漏れの防止に繋がります。
メリット3:情報共有の円滑化とチーム医療の推進
医師、看護師、薬剤師、技師など、多職種がリアルタイムに同じ情報を共有できるため、チーム医療がより円滑に進みます。
- 同時アクセス可能: 複数のスタッフが同時にカルテを閲覧・入力できるため、カンファレンスや申し送りがスムーズになります。
- 院内連携の強化: 他科の受診状況や処方内容もすぐに確認できるため、より質の高い全人的な医療を提供できます。
- 地域医療連携: 紹介状や診療情報提供書の作成が効率化され、地域の他院との連携もスムーズになります。
メリット4:保管スペースと管理コストの削減
物理的な紙カルテがなくなることで、直接的なコスト削減に繋がります。
- 保管スペースの削減: 広大なカルテ庫が不要になり、そのスペースを診察室や病室、スタッフルームなど、より付加価値の高い用途に転用できます。
- 消耗品・管理コストの削減: カルテ用紙、ファイル、インク、印刷代などの消耗品費や、カルテのファイリングや管理にかかる人件費を削減できます。
メリット5:セキュリティ強化とBCP(事業継続計画)対策
紙媒体よりも高度なセキュリティとデータ保全を実現できます。
- 情報漏洩リスクの低減: IDとパスワードによる厳格なアクセス管理や、誰がいつどの情報にアクセスしたかのログを記録することで、不正な閲覧や持ち出しを防ぎます。
- 災害対策: データを定期的にバックアップしておくことで、火災や地震、水害などで病院が被災した場合でも、大切な診療情報を失うことなく、事業の早期復旧が可能になります。
メリット6:診療データの活用による経営改善
電子カルテに蓄積されたデータは、病院経営を分析・改善するための貴重な資源となります。
- 経営指標の可視化: 患者数、疾患別統計、平均在院日数などのデータを容易に抽出・分析し、経営状況の把握や改善策の立案に役立てることができます。
- 各種申請の効率化: DPC(診断群分類包括評価)データの作成や、行政への報告資料作成などが効率化されます。
メリット7:患者サービスの向上
業務効率化は、結果として患者様の満足度向上にも繋がります。
- 待ち時間の短縮: 受付から診察、会計までの一連の流れがスムーズになり、患者様の待ち時間を大幅に短縮できます。
- インフォームドコンセントの充実: 検査画像やデータを画面で見せながら説明することで、患者様の治療への理解を深めることができます。
見過ごせない!紙カルテ電子化の3つのデメリットと対策

多くのメリットがある一方、導入にあたってはデメリットも正しく理解し、事前に対策を講じることが重要です。
デメリット1:高額な導入・運用コスト
電子カルテの導入には、数百万円から数千万円規模の初期投資が必要です。また、導入後も保守費用やライセンス料などのランニングコストが発生します。
- 【対策】
- 補助金・助成金の活用: 「IT導入補助金」や「医療情報化支援基金」など、国や自治体の支援制度を最大限に活用しましょう。
- クラウド型電子カルテの検討: 院内にサーバーを設置するオンプレミス型に比べ、初期費用を抑えられるクラウド型も有力な選択肢です。
デメリット2:システム障害・停電時のリスク
サーバーダウンやネットワーク障害、停電、サイバー攻撃などにより、システムが利用できなくなるリスクがあります。その間、診療がストップしてしまう可能性があります。
- 【対策】
- バックアップ体制の構築: 定期的なバックアップはもちろん、遠隔地での二重バックアップなど、万全のデータ保全策を講じます。
- 非常時対応マニュアルの策定: システムダウン時の運用ルール(紙での代行入力など)を事前に定め、全職員で訓練しておくことが重要です。
- セキュリティ対策の徹底: 信頼性の高いセキュリティ機能を備えたシステムを選び、職員のセキュリティ意識を高める教育も欠かせません。
デメリット3:導入時の業務負担と職員への教育
新しいシステムの導入は、現場の職員にとって大きな負担となります。操作に慣れるまでは一時的に業務効率が低下したり、ITに不慣れな職員から反発が起きたりする可能性もあります。
- 【対策】
- 十分な教育・トレーニング期間の確保: 導入前に十分なトレーニング期間を設け、集合研修や個別指導を丁寧に行います。
- 段階的な導入: まずは特定の診療科や部門からスモールスタートし、徐々に範囲を広げていく方法も有効です。
- 丁寧な合意形成: なぜ電子化が必要なのか、それによってどのようなメリットがあるのかを全職員に丁寧に説明し、理解と協力を得ることが成功の鍵です。
カルテ以外の病院文書管理なら「スペシウム」が解決!

電子カルテを導入して診療情報をペーパーレス化しても、病院運営にはまだまだ多くの紙の書類が残っているのではないでしょうか?
- 地域連携室で交わされる医療機関との「契約書」
- 医薬品や医療機器の購入に関する「請求書」「納品書」
- 総務・人事部門が管理する職員の「雇用契約書」や「各種申請書」
- 行政へ提出する「届出書類」の控え
これらの重要書類の管理に、新たな課題を感じていませんか?
そんな「カルテ以外の書類」の電子化と一元管理に最適なのが、電帳法対応クラウド文書管理システム「スペシウム」です。
電子カルテが「診療情報」の管理に特化しているのに対し、「スペシウム」は病院経営に不可欠なあらゆる「運営文書」を安全かつ効率的に管理することを得意としています。
病院運営を支える「スペシウム」4つの特長
1. 職員が増えても安心!ユーザー数・容量が無制限
月額固定料金で、利用する職員数や保管するデータ容量に上限はありません。全職員にアカウントを付与し、部署ごとに必要な書類を容量を気にせず保管できます。将来的な規模拡大にも柔軟に対応可能です。
2. 経理も安心!電帳法に完全対応
取引先から受領した請求書などの国税関係書類を、電子帳簿保存法の要件を満たして電子保存できます。JIIMA認証を取得しているため、法的に安心してご利用いただけます。
3. 高度なセキュリティと柔軟なアクセス権限設定
部署や役職に応じて「閲覧のみ」「編集可能」など、フォルダごとに細かくアクセス権限を設定できます。個人情報を含む人事関連書類や、経営に関わる重要契約書なども、権限のない職員の目に触れることなく安全に管理できます。
4. 院内の申請・承認プロセスを電子化(Proプラン)
稟議書や物品購入申請などを電子化する「ワークフロー機能」を搭載。院長や事務長が出張中でもスマートフォンから承認でき、院内の意思決定をスピードアップさせます。
電子カルテと「スペシウム」を併用することで、診療から経営まで、病院全体のデジタルトランスフォーメーションを加速させることが可能です。
まとめ

今回は、病院における紙カルテ電子化のメリット・デメリットについて詳しく解説しました。
紙カルテの電子化は、単なる業務効率化ツールではありません。医療の質と安全性を高め、職員の働き方改革を推進し、データ活用による健全な病院経営を実現するための、未来への戦略的投資です。
導入にはコストや労力がかかりますが、それを上回る大きなメリットが期待できます。デメリットと対策を正しく理解し、自院のビジョンに合ったシステムを慎重に選定することで、導入を成功に導くことができるでしょう。
この記事が、貴院の医療DX推進の一助となれば幸いです。