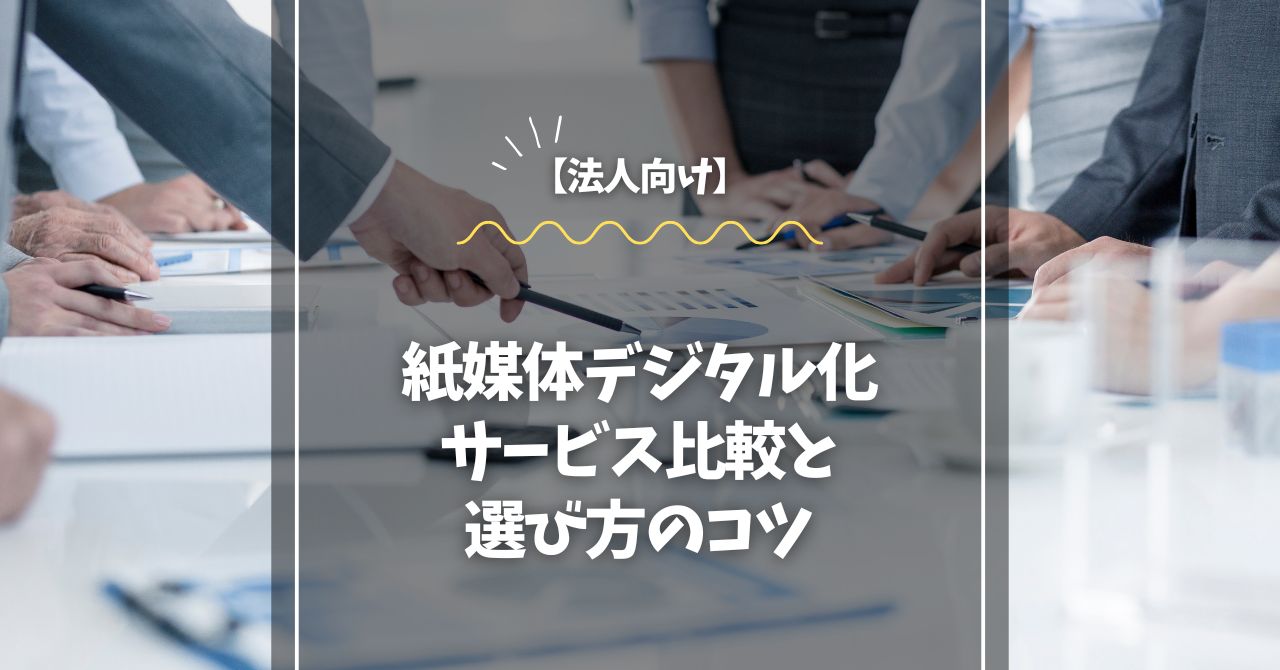「保管スペースが足りない」「書類を探すのに時間がかかる」「テレワークで必要な書類が確認できない」
多くの企業が、日々増え続ける紙媒体の管理にこのような課題を抱えています。これらの課題を根本から解決する手段として、今まさに注目されているのが「紙媒体のデジタル化」です。
しかし、いざデジタル化を進めようとしても、
- 「どんなデジタル化サービスがあるの?」
- 「自社に合ったサービスはどうやって選べばいいの?」
- 「費用はどれくらいかかるんだろう?」
といった疑問が次々と浮かび、なかなか一歩を踏み出せない担当者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、法人向けに紙媒体のデジタル化サービスを検討している担当者様に向けて、サービスの全体像から具体的な比較ポイント、そして失敗しないための選び方のコツまでを網羅的に解説します。自社の課題を解決し、業務効率を飛躍的に向上させる最適なサービスを見つけるためのヒントが満載です。ぜひ最後までご覧ください。
Contents
そもそも紙媒体のデジタル化とは?

紙媒体のデジタル化とは、契約書、請求書、図面、会議資料といった紙の書類をスキャナー等で読み取り、PCやサーバー、クラウド上で閲覧・管理できる電子データに変換することです。一般的に「ペーパーレス化」や「書類の電子化」とも呼ばれます。
単にスキャンして画像データ(PDFやJPEG)にするだけでなく、多くのデジタル化サービスでは、下記のような付加価値を提供しています。
- OCR(光学的文字認識)処理:画像データからテキスト情報を抽出し、ファイル名や本文でのキーワード検索を可能にする技術。
- ファイル名の自動リネーム:設定したルールに基づき、ファイル名を統一し、整理・検索しやすくする。
- 文書管理システム(DMS)への登録:デジタル化したデータをシステムに登録し、高度な検索、アクセス権管理、バージョン管理、保管期限設定などを実現する。
つまり、紙媒体のデジタル化とは、「紙をデータに変える」だけでなく、「企業の情報を資産として活用できる状態にする」ための重要な取り組みなのです。
法人が紙媒体のデジタル化を進めるべき5つのメリット

なぜ今、多くの企業が紙媒体のデジタル化に注目しているのでしょうか。そこには、コスト削減から事業継続まで、企業経営に直結する大きなメリットが存在します。
1. 大幅なコスト削減
物理的な紙がなくなることで、さまざまなコストを削減できます。
- 保管コスト:キャビネットや書庫、外部の倉庫といった保管スペースが不要になり、賃料や管理費を削減できます。
- 印刷・消耗品コスト:紙代、インク・トナー代、ファイル、バインダーなどの購入費用が不要になります。
- 郵送・運搬コスト:契約書や請求書の郵送費、拠点間の書類運搬費が削減できます。
2. 劇的な業務効率の向上
デジタル化による最大のメリットは、業務効率の向上です。特に「検索性」が飛躍的に改善されます。
「あの契約書はどこだっけ?」と書庫を探し回る時間はもうありません。OCR処理された文書は、ファイル名や文書内のキーワードで一瞬にして探し出すことができます。これにより、書類を探すという非生産的な時間が削減され、本来のコア業務に集中できるようになります。
また、情報共有もスムーズになり、承認プロセスなども迅速化します。
3. BCP(事業継続計画)対策の強化
地震や水害などの自然災害、あるいは火災といった不測の事態が発生した際、紙媒体の書類は消失・破損するリスクが非常に高いです。重要な契約書や顧客情報が失われれば、事業の継続が困難になる可能性もあります。
データをクラウド上などにバックアップしておくことで、万が一の際にも重要な情報を保全し、事業を迅速に復旧させることが可能になります。これは、企業の存続に関わる重要なリスク管理(BCP対策)と言えるでしょう。
4. セキュリティとコンプライアンスの強化
「紙の方が安全」と思われがちですが、実際には盗難、紛失、不正な持ち出し、覗き見など、多くのリスクに晒されています。
デジタル化し、文書管理システムで管理することで、以下のような高度なセキュリティ対策が可能になります。
- アクセス権限設定:役職や部署ごとに閲覧・編集・削除の権限を細かく設定。
- アクセスログ管理:「誰が」「いつ」「どのファイルに」アクセスしたかの記録を追跡。
- 暗号化:データの不正な読み取りを防止。
これにより、情報漏洩リスクを低減し、内部統制やコンプライアンスを強化できます。
5. テレワーク・多様な働き方への対応
新型コロナウイルスの影響以降、テレワークは多くの企業で定着しました。しかし、「承認印をもらうためだけに出社する」「必要な資料が会社にしかなく、業務が進まない」といった「ペーパーレス化の壁」に直面した企業も少なくありません。
紙媒体をデジタル化することで、いつでもどこでも必要な情報にアクセスできる環境が整い、場所を選ばない柔軟な働き方を推進できます。
【失敗しない】法人向け紙媒体デジタル化サービスの選び方と比較ポイント

デジタル化のメリットを最大限に享受するためには、自社の目的や状況に合ったサービスを選ぶことが不可欠です。ここでは、サービス選定で失敗しないための7つの比較ポイントを解説します。
ポイント1:対応書類の種類と品質
まず、自社がデジタル化したい書類の種類に対応しているかを確認しましょう。
- 一般文書:A4、A3サイズの定型書類
- 契約書・重要書類:ホチキス留め、製本された書類
- 図面:A2以上の大判サイズ、青焼き図面
- 書籍・カタログ:裁断が必要か、非破壊でスキャンできるか
- マイクロフィルム:専用の機材が必要
スキャンの解像度(dpi)やカラー/モノクロ、ファイル形式(PDF, TIFFなど)の指定が可能かどうかも重要です。特に図面や写真を含む文書は、高解像度でのスキャンが求められます。
ポイント2:セキュリティ対策
企業の機密情報や個人情報を含む書類を外部に預けるため、セキュリティ対策は最も重要なチェック項目です。
- 認証資格の有無:プライバシーマーク(Pマーク)、ISMS(ISO27001)認証を取得しているか。
- 物理的セキュリティ:作業場所への入退室管理、監視カメラの設置状況。
- 人的セキュリティ:従業員との機密保持契約、セキュリティ教育の実施。
- ネットワークセキュリティ:データ転送時の暗号化(SSL/TLSなど)。
サービス提供会社のウェブサイトや資料で、セキュリティポリシーを必ず確認しましょう。
ポイント3:料金体系
料金体系はサービスによって大きく異なります。トータルコストを正確に把握するために、以下の項目を確認しましょう。
| 費用項目 | 説明 |
|---|---|
| 初期費用 | 基本料金、コンサルティング費用など、導入時に一度だけかかる費用。 |
| スキャニング費用 | 「1枚あたり〇円」「1箱あたり〇円」といった従量課金。サイズやカラー/モノクロで変動。 |
| 月額費用 | 文書管理システムを利用する場合のシステム利用料やサーバー保守費用。 |
| オプション費用 | OCR処理、ファイル名変更、ホチキス外し、原稿の廃棄など、基本サービス以外の費用。 |
「スキャン料金が安く見えても、オプションを付けると高額になった」というケースも多いため、必要な作業を含めた総額で見積もりを取得することが重要です。
ポイント4:OCR(文字認識)の精度と機能
検索性を高めるためにはOCRの精度が鍵となります。特に、手書き文字や低画質の印字、専門用語を含む文書を扱う場合は、高精度なAI-OCRに対応したサービスがおすすめです。
また、特定の項目(日付、取引先名、金額など)を自動で読み取り、データ化してくれる機能があると、後のデータ活用が格段に楽になります。
ポイント5:文書管理システム(DMS)との連携
デジタル化したデータをどのように管理・活用するかは非常に重要です。スキャニング代行のみを依頼するのか、その後の管理まで任せるのかを明確にしましょう。
- 既存の社内システムやファイルサーバーで管理するのか?
- サービス提供会社が提供する文書管理システムを新たに導入するのか?
- 他社のクラウドストレージ(Google Drive, Dropboxなど)と連携できるか?
将来的な運用を見据えて、拡張性や連携のしやすさを確認することが大切です。
ポイント6:法改正への対応(特に電帳法)
近年、電子帳簿保存法(電帳法)が改正され、国税関係書類(請求書、領収書、契約書など)の電子保存に関する要件が大きく変わりました。電子取引データの電子保存が義務化されるなど、企業は法対応を迫られています。
選ぶサービスやシステムが、この電帳法の要件(真実性の確保、可視性の確保)を満たしているかは、コンプライアンス上、極めて重要な比較ポイントです。JIIMA認証(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会が電帳法の要件を満たすと認証した製品に与えられるマーク)を取得しているサービスは、信頼性の一つの目安になります。
ポイント7:サポート体制と導入実績
導入時のコンサルティングから、運用開始後のトラブルシューティングまで、手厚いサポート体制があるかを確認しましょう。特に初めて紙媒体のデジタル化に取り組む企業にとっては、専門家のサポートは心強い味方になります。
また、自社と同じ業種や企業規模での導入実績が豊富かどうかも確認しましょう。業界特有の書類や業務フローへの理解が期待でき、スムーズな導入につながります。
電帳法対応ならクラウド文書管理システム「スペシウム」がおすすめ

ここまで紙媒体デジタル化サービスの選び方を解説してきましたが、「法改正への対応が特に重要だ」「高精度なOCRで業務を自動化したい」とお考えの企業様に、ぜひご紹介したいのがクラウド文書管理システム「スペシウム」です。
スペシウムは、単なる書類保管庫ではありません。改正電子帳簿保存法やインボイス制度に完全対応し、企業の文書管理を次のステージへと引き上げるための強力な機能を多数搭載しています。
スペシウムのここがすごい!3つの特徴
1. 【安心】改正電帳法・インボイス制度に完全対応!
法対応は企業の文書管理における最重要課題です。スペシウムは、電帳法の法的要件を満たすソフトウェアに与えられる「JIIMA認証」を取得しています。
JIIMA認証(電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証・電子取引ソフト法的要件認証)を取得しているため、請求書や領収書などの国税関係書類を、法令要件を遵守しながら安心して電子保存することが可能です。
インボイス制度にも対応しており、適格請求書発行事業者の登録番号を読み取り、国税庁のデータベースと照合・確認する機能も備えています。法務・経理部門の負担を大幅に軽減し、コンプライアンスを盤石にします。
2. 【効率化】高精度AI-OCRで入力作業を自動化
スペシウムは、独自の高精度AI-OCRエンジンを搭載しています。アップロードされた請求書や領収書から、「取引年月日」「取引金額」「請求書発行元」などの情報を自動で読み取り、データ化します。
- 手入力の手間とミスを撲滅:面倒なデータ入力作業から解放され、ヒューマンエラーを防ぎます。
- 検索性の向上:読み取ったデータは全て検索対象となり、必要な書類を瞬時に見つけ出せます。
- 会計ソフト連携:出力したCSVデータを会計ソフトに取り込むことで、仕訳作業も効率化できます。
これにより、バックオフィス業務の生産性を劇的に向上させることが可能です。
3. 【簡単・安全】誰でも使える操作性と強固なセキュリティ
「新しいシステムは操作を覚えるのが大変…」という心配は不要です。スペシウムは、ITが苦手な方でも直感的に操作できるシンプルな画面設計を追求しています。
もちろん、セキュリティも万全です。金融機関レベルのセキュリティを誇る国内データセンターでデータを厳重に管理。不正アクセス防止機能、IPアドレス制限、操作ログの記録など、企業の重要情報を守るための機能が充実しており、安心してご利用いただけます。
紙媒体のデジタル化を検討する上で、特に「法対応」と「業務効率化」を重視するなら、スペシウムは最適な選択肢の一つです。ご興味のある方は、ぜひ公式サイトで詳細をご確認ください。
まとめ:自社に最適なサービスで、紙媒体のデジタル化を成功させよう

本記事では、法人向けの紙媒体デジタル化サービスについて、そのメリットから具体的な比較ポイント、選び方のコツまでを詳しく解説しました。
紙媒体のデジタル化は、もはや単なるコスト削減や業務効率化の手段ではありません。BCP対策、セキュリティ強化、そして多様な働き方への対応といった、現代企業が抱える経営課題を解決するための戦略的な投資です。
成功の鍵は、「なぜデジタル化するのか?」という目的を明確にし、自社の課題や状況に最適なサービスを慎重に選ぶことにあります。
今回ご紹介した7つの比較ポイントを参考に、ぜひ複数のサービスを比較検討してみてください。そして、法対応やAI-OCRによる自動化を重視する場合は、クラウド文書管理システム「スペシウム」のような高機能なツールの導入も視野に入れることをおすすめします。
この記事が、貴社のペーパーレス化推進の一助となれば幸いです。