オフィスのキャビネットや倉庫に眠る大量の紙文書。「ペーパーレス化を進めたいけれど、紙文書のデータ化にかかる料金が気になって一歩踏み出せない…」そんなお悩みをお持ちではないでしょうか?
紙文書のデータ化(スキャニングサービス)は、業務効率化やDX推進に不可欠ですが、その費用は決して安くありません。しかし、いくつかのポイントを押さえるだけで、データ化の料金を大幅に安く抑えることが可能です。
この記事では、紙文書のデータ化にかかる料金の内訳や相場を解説するとともに、誰でも実践できる「料金を安く抑えるための具体的な3つの方法」を徹底的にご紹介します。さらに、データ化後の活用に欠かせない、電子帳簿保存法に対応した文書管理システムについても触れていきます。
この記事を読めば、コストを賢く管理しながら、スムーズに紙文書のデータ化を進める知識が身につきます。ぜひ最後までご覧ください。
Contents
まずは基本から!紙文書データ化の料金内訳

料金を安くする方法を知る前に、まずは「何に」「いくら」かかっているのか、その内訳を正しく理解することが重要です。紙文書のデータ化にかかる料金は、大きく分けて「基本料金」と「オプション料金」の2つで構成されています。
基本料金:スキャニングそのものにかかる費用
基本料金は、紙文書をスキャンしてPDFなどの電子ファイルに変換する作業そのものに対する費用です。一般的に「1枚あたり〇円」という単価で設定されています。
この単価は、以下の要素によって変動します。
- 書類のサイズ:A4、A3、A0、図面など、サイズが大きくなるほど料金は高くなります。
- カラーモード:「カラー」「グレースケール」「モノクロ2値」の順に料金が高くなるのが一般的です。
- 解像度(dpi):画像のきめ細かさを示す単位。解像度が高いほどデータは綺麗になりますが、料金も上がります。
多くの業者は、最も一般的な「A4サイズ・モノクロ」を基準料金として提示しています。
オプション料金:付帯サービスにかかる費用
オプション料金は、基本的なスキャニング作業に加えて発生する、様々な付帯サービスに対する費用です。知らずに依頼すると、思った以上に総額が高くなってしまうケースがあるため、注意が必要です。
どのようなオプションがあるのか、料金の目安とともに下記の表で確認してみましょう。
| オプション項目 | サービス内容 | 料金の目安 |
|---|---|---|
| ファイリング作業 | ホチキスやクリップ、付箋の取り外し、書類の向きを揃えるなど、スキャン前の準備作業。 | 1枚あたり1円~5円 |
| ファイル名変更 | スキャンしたデータに、契約書番号や日付など、指定のルールでファイル名を付ける作業。 | 1ファイルあたり10円~50円 |
| フォルダ作成・階層化 | 「年度別」「部署別」など、指定のルールでフォルダを作成し、データを整理する作業。 | 1フォルダあたり10円~ |
| OCR処理 | 画像データからテキスト情報を抽出し、全文検索を可能にする処理。 | 1枚あたり1円~10円 |
| 原本の保管・廃棄 | スキャン後の紙文書を一定期間保管したり、溶解処理などで安全に廃棄したりするサービス。 | 段ボール1箱あたり月額数百円~(保管) 1kgあたり数十円~(廃棄) |
| 出張スキャニング | 社外に持ち出せない機密文書などを、依頼者のオフィスでスキャンするサービス。 | 別途見積もり(高額になる傾向) |
このように、一口に「紙文書のデータ化」と言っても、どこまで業者に任せるかによって料金は大きく変わってきます。これが、料金を安く抑えるための最初のヒントになります。
紙文書データ化の料金相場は?

では、具体的な料金相場はどのくらいなのでしょうか。業者や依頼枚数によって変動しますが、一般的なスキャニングの料金相場をまとめました。
| 書類サイズ | モノクロ2値 | グレースケール | カラー |
|---|---|---|---|
| A4/B5 | 3円~8円 | 4円~10円 | 5円~15円 |
| A3/B4 | 6円~16円 | 8円~20円 | 10円~30円 |
| A2~A0(図面など) | 200円~ | 300円~ | 400円~ |
※上記は解像度200~300dpiの場合の目安です。
※大量発注(10万枚以上など)の場合は、単価が割引されることが多くあります。
例えば、A4のカラー文書を1万枚データ化する場合、基本料金だけで5万円~15万円ほどの費用がかかる計算になります。これにオプション料金が加わるため、総額を意識した計画が重要です。
【本題】紙文書データ化の料金を安く抑える3つの方法

お待たせしました。ここからは、本題である「紙文書データ化の料金を安く抑えるための具体的な3つの方法」について、詳しく解説していきます。どれもすぐに実践できることばかりですので、ぜひ参考にしてください。
方法1:自社でできる作業は自分たちで行う(事前準備の徹底)
最も効果的で、すぐに取り組めるコスト削減方法が「事前準備の徹底」です。先ほどの料金内訳で見たように、ホチキスを外したり、書類を整理したりする作業はオプション料金として加算されます。これらの作業を自社で行うだけで、大きな費用削減に繋がります。
具体的には、業者に依頼する前に以下の作業を済ませておきましょう。
- ホチキス、クリップ、バインダーを全て外す
スキャナーの故障原因にもなるため、最も重要な作業です。一つ残らず丁寧に取り除きましょう。 - 付箋を剥がす、またはスキャン可能な位置に移動する
文字の上に貼られている付箋は、スキャン時に隠れてしまいます。内容を転記して剥がすか、文字にかからない空白部分に貼り直しましょう。 - スキャン不要な書類を取り除く
データ化する必要のないメモ書き、重複した書類、裏紙などを事前に分別し、スキャン対象の枚数そのものを減らします。 - 書類をサイズごとに仕分ける
A4とA3が混在している場合、事前に分けておくと業者の作業がスムーズになり、料金が安くなる場合があります。 - 書類の向きを揃える
天地がバラバラのままだと、向きを修正するオプション料金がかかる可能性があります。
これらの作業は手間がかかりますが、社員やアルバイトで対応することで、外注費を大幅に削減できます。「業者に依頼する作業範囲を最小限にする」という意識を持つことが、コストカットの第一歩です。
方法2:スキャニングの仕様を最適化する
「とりあえず高画質で全部カラーで」と考えていませんか?その判断が、不要なコストを生んでいるかもしれません。データ化する文書の用途に合わせて、スキャニングの仕様を最適化することも、料金を安く抑えるための重要なポイントです。
見直すべき仕様は主に3つあります。
① 解像度
契約書や申請書など、テキスト情報が中心の一般的なビジネス文書であれば、200~300dpi(dots per inch)の解像度で十分です。これ以上の高解像度(400dpiや600dpi)は、写真や図面など、細部まで鮮明に残したい場合にのみ選択しましょう。解像度を上げるとデータ容量が大きくなり、料金も高くなります。
その文書、本当に高解像度でスキャンする必要はありますか? 用途を明確にし、必要十分な解像度を選ぶことが賢明です。
② カラーモード
見積書や請求書など、文字情報がメインで印鑑の色なども特に重要でない文書は、「モノクロ2値」や「グレースケール」でスキャンすることで料金を抑えられます。カラーでのスキャンは、パンフレットや写真、色分けされた図など、色が重要な情報を持つ文書に限定しましょう。
「全てカラーで」と一括りにせず、文書の種類ごとに最適なカラーモードを指定することで、全体の費用を大きく削減できます。
③ OCR処理
OCR(光学的文字認識)処理は、スキャンした画像データからテキストを抽出し、ファイル内のキーワードで検索できるようにする非常に便利な機能です。しかし、全ての文書にキーワード検索が必要とは限りません。
例えば、「ファイル名(例:2023年度契約書_A社.pdf)」だけで管理・検索が十分な文書であれば、OCR処理は不要かもしれません。本当に全文検索が必要な文書群にのみOCR処理を依頼することで、オプション料金を節約できます。
方法3:複数の業者から相見積もりを取る
最後の方法は、基本中の基本でありながら最も重要な「相見積もり」です。紙文書データ化の料金は、業者によって驚くほど差があります。1社だけの見積もりで判断してしまうと、知らないうちに相場より高い料金を支払うことになりかねません。
必ず、最低でも3社以上から見積もりを取り、料金とサービス内容を比較検討しましょう。
相見積もりを取る際のポイントは以下の通りです。
- 同じ条件で見積もりを依頼する
枚数、書類サイズ、カラーモード、解像度、希望するオプションなど、全社に同じ条件を伝えないと、正確な比較ができません。 - 料金の内訳を細かく確認する
「一式」で料金が提示されている場合は要注意。基本料金とオプション料金の内訳を明確にしてもらい、何にいくらかかっているのかを把握しましょう。 - 品質とセキュリティ体制も比較する
料金の安さだけで選ぶのは危険です。スキャンの品質(サンプルスキャンを依頼するのがおすすめ)や、情報漏洩を防ぐセキュリティ体制(プライバシーマークやISMS認証の有無など)もしっかり比較しましょう。
料金の安さだけに惹かれて業者を選ぶと、「スキャンした画像の文字が潰れて読めない」「納品されたデータのファイル名がバラバラで整理できない」といった品質トラブルや、「預けた書類を紛失された」などの重大なセキュリティ事故に繋がるリスクがあります。料金と品質、セキュリティのバランスを総合的に判断することが、業者選びで失敗しないための鍵となります。
複数の業者を比較することで、自社の予算と要求に最も合った、コストパフォーマンスの高いサービスを見つけることができます。
データ化後の活用が成功の鍵!電帳法対応ならクラウド文書管理システム
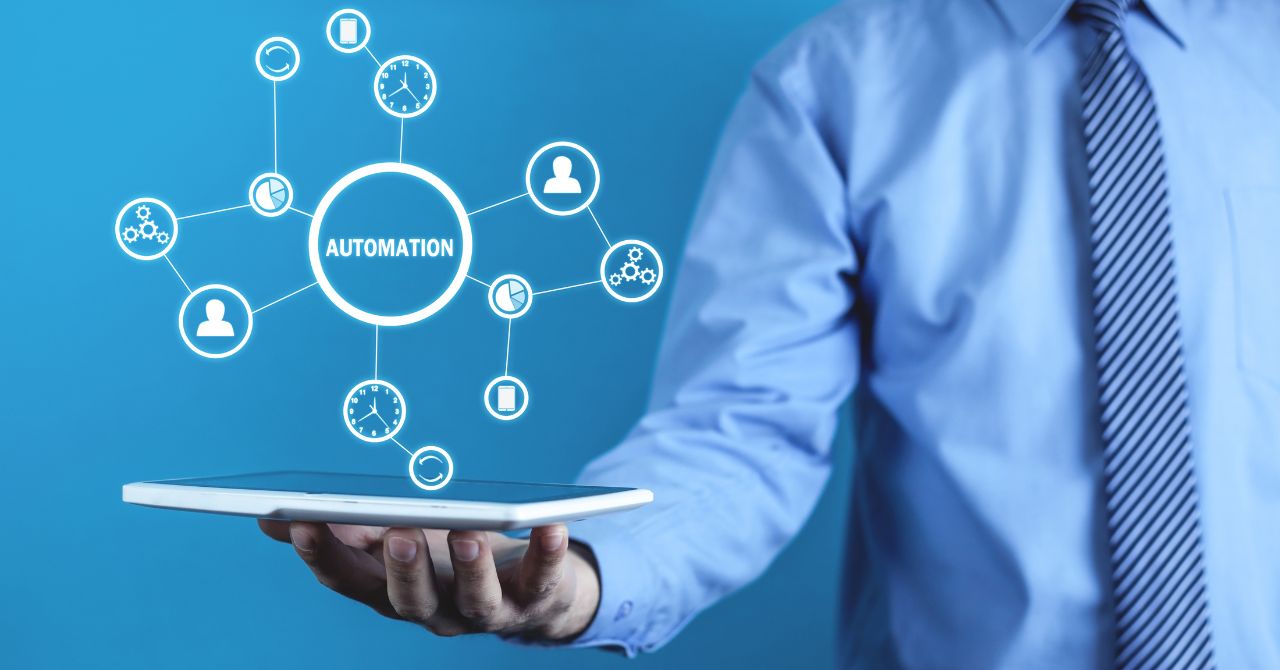
ここまで、紙文書データ化の料金を安く抑える方法をご紹介してきました。しかし、忘れてはならないのが、「データ化はゴールではなく、スタートである」ということです。
時間とコストをかけてデータ化した文書も、ただサーバーに保存しておくだけでは宝の持ち腐れです。必要な情報をいつでも誰でも迅速に検索・活用できる環境を整えて、初めてデータ化の真価が発揮されます。
特に近年では、電子帳簿保存法(電帳法)への対応が多くの企業で急務となっています。国税関係の書類(請求書、領収書、契約書など)を電子データとして保存するには、法律で定められた要件を満たす必要があります。
そこでおすすめなのが、JIIMA認証(※)を取得したクラウド文書管理システムの導入です。
※JIIMA認証:公益社団法人日本文書情報マネジメント協会が、電帳法の要件を満たすソフトウェアを認証する制度。
電帳法対応と業務効率化を両立するなら「スペシウム」

紙文書のデータ化から、法対応、そして日々の業務での活用までをワンストップで実現したい。そんな企業様にご紹介したいのが、クラウド文書管理システム「スペシウム」です。
>> 電帳法対応クラウド文書管理システム「スペシウム」公式サイトはこちら
「スペシウム」の主な特徴
- 安心の電帳法対応:JIIMA認証(「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」および「電子取引ソフト法的要件認証」)を取得済み。安心して国税関係書類を保存できます。
- AI-OCRで高精度にデータ化:高性能なAI-OCRを標準搭載。スキャンした書類から取引先名、日付、金額などの情報を自動で読み取り、手入力の手間を大幅に削減します。
- 強力な検索機能:全文検索はもちろん、読み取った日付や金額での範囲指定検索など、多彩な検索機能で目的の書類を瞬時に見つけ出します。
- 直感的な操作性:誰でもマニュアルなしで使える、シンプルで分かりやすいインターフェース。システム導入のハードルを下げ、社内への浸透をスムーズにします。
- 万全のセキュリティ:通信の暗号化やIPアドレス制限、操作ログの管理など、企業の重要文書を預けるのにふさわしい堅牢なセキュリティ体制を構築しています。
紙文書のデータ化を外部業者に依頼し、納品されたデータを「スペシウム」にアップロードするだけで、法対応と劇的な業務効率化を同時に実現できます。
「データ化後の管理方法が決まっていない」「電帳法への対応に不安がある」という方は、ぜひ一度「スペシウム」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ

今回は、紙文書データ化の料金を安く抑えるための3つの具体的な方法について解説しました。
【料金を安く抑える3つの方法】
- 自社でできる作業は自分たちで行う(事前準備の徹底)
- スキャニングの仕様(解像度・カラーモード・OCR)を最適化する
- 複数の業者から相見積もりを取って比較検討する
これらのポイントを実践するだけで、紙文書のデータ化にかかる費用は大きく変わってきます。まずはデータ化したい書類を整理し、どこまでの作業を自社で行い、どのような仕様で依頼するのかを明確にすることから始めましょう。
そして、データ化を成功させるためには、その後の活用を見据えた計画が不可欠です。信頼できる業者選びと、「スペシウム」のような優れた文書管理システムを組み合わせることで、ペーパーレス化のメリットを最大限に引き出すことができます。
本記事が、貴社のコスト削減とDX推進の一助となれば幸いです。


