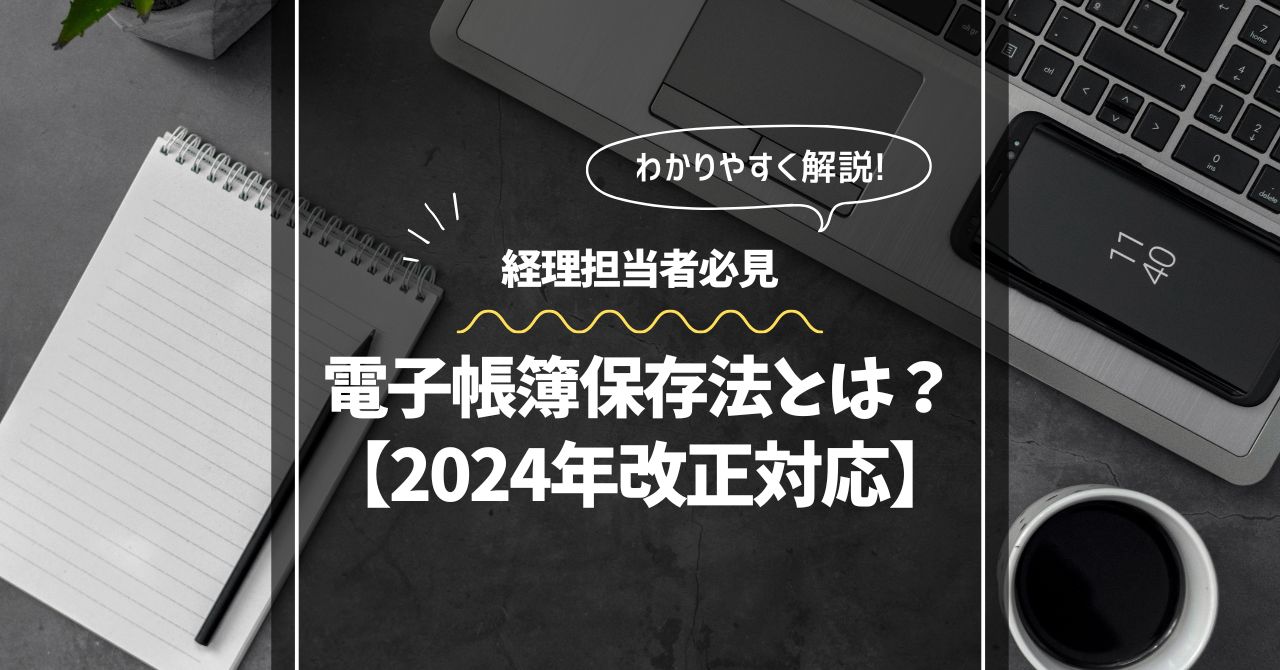近年、企業のデジタル化を推進する上で重要な役割を担っているのが「電子帳簿保存法」です。しかし、名前は聞いたことがあっても、具体的にどのような法律なのか、どのような対応が必要なのか、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。
本記事では、電子帳簿保存法の概要から、対象となる書類、保存要件、改正のポイント、そして中小企業が対応するための具体的なステップまで、わかりやすく解説します。
この記事を読めば、電子帳簿保存法について理解を深め、スムーズな対応を進めることができるでしょう。
電子帳簿保存法の概要

電子帳簿保存法は、正式名称を「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といいます。
この法律は、従来紙で保存することが義務付けられていた国税関係帳簿書類について、一定の要件を満たすことで電子データによる保存を認めるものです。
- 目的: 税務手続きの効率化、コスト削減、ペーパーレス化の推進
- 対象: 国税関係帳簿書類(帳簿、書類、請求書、領収書など)
- 保存方法: 電子帳簿保存、スキャナ保存、電子取引データ保存の3種類
電子帳簿保存法は、1998年に制定されて以降、時代の変化に合わせて改正が繰り返されてきました。
特に近年では、2022年と2024年に大きな改正が行われ、企業におけるデジタル化への対応を後押しする内容となっています。
電子帳簿保存法の対象となる書類
電子帳簿保存法の対象となる書類は、大きく分けて以下の3種類です。
- 電子帳簿保存: 会計ソフトなどで作成した帳簿を、データのまま保存する方法です。
- スキャナ保存: 紙で受領・作成した書類をスキャナで読み取り、画像データとして保存する方法です。
- 電子取引データ保存: インターネット取引などで授受した請求書や領収書などの電子データを、データのまま保存する方法です。
それぞれの保存方法によって満たすべき要件が異なります。
電子帳簿保存の要件
電子帳簿保存法に基づいて電子データを保存するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 真実性の確保:
- 訂正・削除履歴の確保
- 相互関連性の保持
- 検索機能の確保
- 可視性の確保:
- 見読性の確保(ディスプレイなどで明瞭に確認できること)
- 検索機能の確保(日付、金額、取引先などで検索できること)
これらの要件を満たすためには、適切なシステムを導入したり、運用ルールを整備したりする必要があります。
### 電子帳簿保存法の改正ポイント【2024年】
2024年に行われた電子帳簿保存法の改正では、主に以下の点が変更されました。
- 電子取引データの保存義務化: 2024年1月1日以降、電子的に授受した請求書や領収書などの電子取引データは、原則としてデータのまま保存することが義務付けられました。
- 宥恕(ゆうじょ)措置の廃止: 以前は、一定の要件を満たせば、電子取引データを紙で保存することも認められていましたが、2024年以降は原則として認められなくなりました。
- 検索要件の緩和: 一部の事業者に対して、検索要件が緩和されました。
特に、電子取引データの保存義務化は、多くの企業に影響を与える改正です。
### 中小企業が電子帳簿保存法に対応するためのステップ
電子帳簿保存法への対応は、中小企業にとって負担に感じるかもしれませんが、以下のステップで進めることで、スムーズな導入が可能です。
- 現状の把握: まずは、自社でどのような国税関係帳簿書類を扱っているのか、どのような方法で保存しているのかを把握します。
- 課題の洗い出し: 次に、現状の保存方法で電子帳簿保存法の要件を満たせない部分を洗い出します。
- 対応策の検討: 課題を踏まえ、どのようなシステムを導入するのか、どのような運用ルールを整備するのかを検討します。
- システムの導入・運用ルールの整備: 検討結果に基づき、システムを導入し、運用ルールを整備します。
- 従業員への周知・研修: 従業員に電子帳簿保存法の概要や変更点、新しい運用ルールを周知し、研修を行います。
中小企業向けのクラウド会計ソフトの中には、電子帳簿保存法に対応した機能が搭載されているものもあります。
このようなシステムを活用することで、比較的容易に電子帳簿保存法に対応することができます。
電子帳簿保存法に関するFAQ

電子帳簿保存法に関してよくある質問とその回答をまとめました。
Q. 電子帳簿保存法に対応しないと罰則はありますか?
A. 電子帳簿保存法の要件を満たさずに保存した場合、税務調査で指摘を受け、追徴課税や加算税が課される可能性があります。また、青色申告の承認が取り消される可能性もあります。
Q. スキャナ保存のタイムスタンプは必須ですか?
A. はい、スキャナ保存を行う場合、改ざん防止のためにタイムスタンプの付与が原則として必要です。
Q. 電子取引データの保存場所はどこが良いですか?
A. 電子取引データの保存場所は、自社の環境に合わせて選択できます。クラウドストレージや社内サーバーなどが考えられますが、データの安全性や検索性を考慮して選択する必要があります。
まとめ

電子帳簿保存法は、企業のデジタル化を推進するための重要な法律です。特に2024年の改正では、電子取引データの保存義務化が導入され、多くの企業が対応を迫られています。
本記事で解説した内容を参考に、電子帳簿保存法への理解を深め、自社に合った対応を進めていきましょう。
中小企業向けのクラウド会計ソフトなどを活用することで、比較的容易に対応することができます。
最新の情報は必ず国税庁のホームページで確認するようにしてください。
電子帳簿保存法にも対応!書類の電子化ならスペシウム
スペシウムは大量の書類を電子化して保管ができます。
電子帳簿保存法にも対応していますので、是非お問い合わせ下さい!